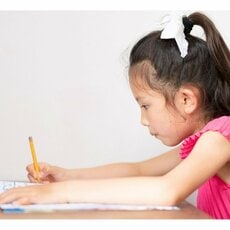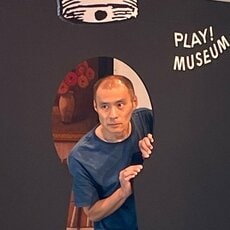矢萩:そうそう。ずっと第1希望だって言っているのに、ホームページすらちゃんと見たことがないというのもよくある話です。
安浪:教え子たちに学校見学の感想を聞くと、「よかった」と言うか「うーん……」と言うか、この二つの反応のどちらかが多いです。というか小学生はその程度。だからこそ「どういうところがよかったの?」と、どんどん掘り込んで聞いていくと、いくつか細かい項目が出てくるんですよね。「みんなが挨拶してくれた」とか「トイレが汚かった」とか(笑)。子どもなりに細かいところを見た上で、全体の印象を言っているんです。
矢萩:僕も同じようなことをやりますね。「行ってきた学校のよかったところを3つ挙げて」と聞きます。同時に、「いまいちだったところも3つ挙げてみて」と言うんです。そうするとその子がその学校のどこがいいと思っていて、どこが悪いと思っているかの視点や価値観が見えてきます。
■第六感は侮れない
安浪:あとは「何となくよかった(イマイチだった)」というのもあるあるです。その場合は、親が言語化してあげると「たしかに、駅から学校までの雰囲気がイヤだった」など明確になることもあります。でも、言語化できない第六感で学校を評価している場合も侮れません。だからこそ、親御さんが感想を聞くときは、そういった子どもの素直な感想も尊重してあげてほしいです。
矢萩:受験生自身がいちばんリアリティーを持てるようになるのは、その学校に通っている生徒と対話することだと思います。学校でイベントなどがあったら行って話を聞くのもいいし、紹介してもらって学外で会うのでもいいでしょう。対話をしてみて、わくわくできるか、その学校に行きたいなって思えるか、あるいは違和感がないか、というのを確認する作業はすごく大事だと思います。もちろん生徒だけでなく、先生との対話でもいいんです。体験授業に行って、何かやったときに先生が声をかけてくれて、「それがきっかけでうちの子、火がつきました」、という話をされる保護者の方も結構います。
次のページへ2月1日に「この学校じゃないと思った」