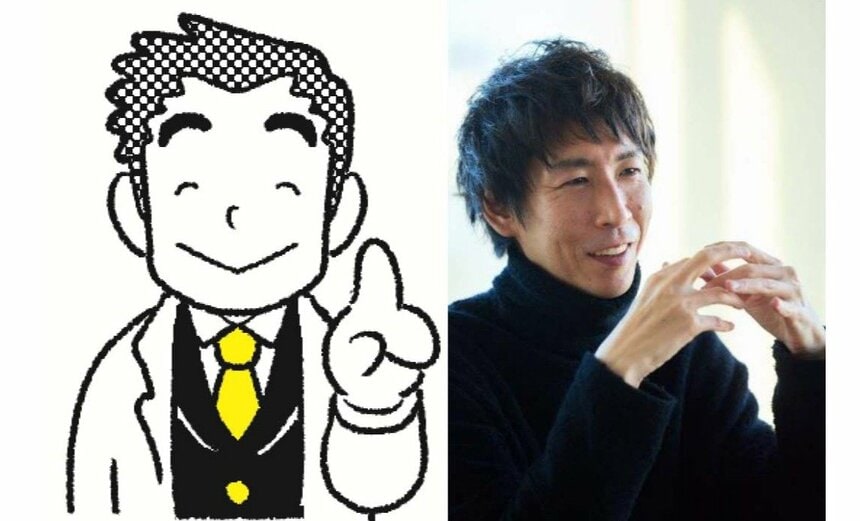中学受験。それは単なる学力競争ではなく、「親子の共同プロジェクト」と呼ばれて久しい。実際に、中学受験を選ぶ保護者たちは、どのように子どもと意思決定をしているのか。
【マンガ】中学受験で合格したのに…「やっぱり地元の公立中に行く」 息子の告白に両親が出した“答え”とは?(全35枚)『「中学受験」をするか迷ったら最初に知ってほしいこと』で受験の意義を問い続ける塾講師の東京高校受験主義・東田高志氏と、中学受験に挑む娘と父を描いた小説『問題。以下の文章を読んで、家族の幸せの形を答えなさい』の著者である早見和真氏が中学受験を本音で語り合った。 ※前編〈中学受験は「人生を選び取る第一歩」か、それとも「親子の不安の共有」か 作家・早見和真×東京高校受験主義対談〉 から続く
* * *
“自分の道を正解にする”という考え方
――東田氏が提唱する「戦略的高校受験」。高校受験でしか得られないたくさんのメリットを知ってほしいという。「高校受験の塾講師がなぜ、中学受験の情報を発信するのか!」といった批判も届くが、強く伝えたいのは、「第1志望に受からなきゃ不幸になる」という刷り込みを取り払うことだと強調する。
東田:大人になった生徒から学生時代の思い出を聞いていると「親からの言葉が今でも忘れられない」「大人になった今でも母親を100%信用できない」と話す人が多いんです。
思春期に入る前だと、子どもは親に対して従順です。親は忘れたひと言でも、子どもはずっと覚えている。逆に高校受験を考える14~15歳になると、受験を「自分事」として捉えられるようになります。当事者意識を持てるようになってから、受験という壁に当たるべきだと私は強く思っています。
早見:12歳あるいは15歳という時期に悔しい経験をしたことによって、その後の人生が豊かになる子どももいると僕は信じたいんですよね。
持論ですが、志望校に合格したからといって幸せになれる確率は50%だと思いますし、受験で失敗したとしても幸せになれる確率もまた50%あると思っています。
東田:高校受験も同じです。子どもは想像以上に、第1志望に受からないと不幸になると思い込んでいる。大人の役割は、その刷り込みを取ってあげること。「自分の道を正解にしていくこと」が大切であり、第1志望に受かったその道は決して、正解だとはいえないのです。
次のページへ公立中学校への“誤解”