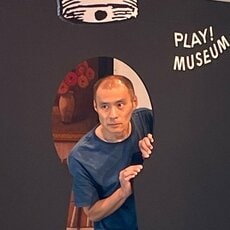二人のお子さんを育てるヨシタケシンスケさん。絵本作家としてではなく、ひとりの父親として、わが子に向き合うことの難しさ、お子さんが中学受験を経験した際の親としての葛藤、そして子どもたちを遠くから見守る大切さについてお話を伺いました。後編<ヨシタケシンスケ「子どもたちの近くには、親や先生と違う適切な距離の“ちょっと変な”大人が必要」 新作絵本に込めた“思い”とは>に続く
【マンガ】中学受験で「偏差値の高い学校」への思いを捨てきれなかった母が「路線変更」を決断して“わかった”こととは?(全38枚)絵本では「逃げていい」「やめていい」と発信。けれど…
――ヨシタケさんの二人の息子さんたちは、中学受験を経験されたと聞きました。ヨシタケさんはお子さんの受験勉強にどのように関わられましたか?
そうなんですよ……。受験は本当に大変でした。それでも、上の子はどちらかというと受験勉強に向いていたほうだと思います。ですから、わりとすんなりと進んだのですが、下の子が、とても苦労してしまった。見ていて、かわいそうでした。
僕はいつも、絵本の中で、本当につらい時は「逃げていい」「やめていい」というメッセージを発信しています。しかし、親としての立場になると、自分の子どもに「逃げるな」と言わなくてはいけなかった。自分が本心で思っていることと異なることを伝えなくてはいけないのが、本当につらかったですね。
――中学受験は向き不向きもありますよね……。
正直、こんな苦労を小学校5、6年生ですることが本当にいいことなのか、と疑問でした。子どもたちの最も多感な時期に、大切な子どもの時間を、受験勉強に注ぎ込むのがいいのだろうか、とずいぶん悩みましたね。
うちの子たちだけでなく、周囲のご家庭や子どもたちの葛藤を見ても思いましたし、受験が終わった後もずっと「あれでよかったのか?」と迷っていました。
ただ、このシステムは、なかなか一人の保護者の意見で変わるものじゃないし、受験の仕組みも、おそらく数年では、変わっていかないと思います。
もちろん、受験勉強をすることで成長する子もいるし、それが向いている子もいます。でも、同時に、中学受験が向いていない子もいるということは、大人は知っておいたほうがいいと思います。
次のページへ失敗体験を財産にするために