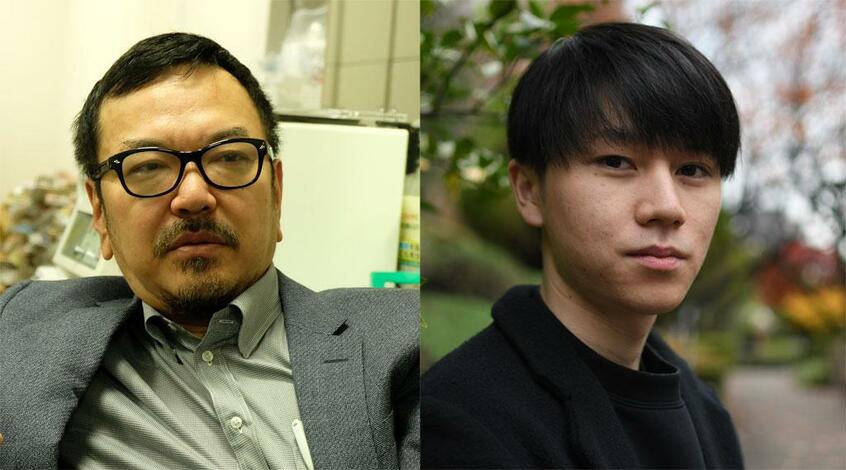
和田:今回事件を起こした少年は、生徒会に立候補したり、学校行事にも積極的に取り組んだり、外から見た限りでは社交的なんです。でも、本音を打ち明けることはできなかったように思えます。それがなぜかは少年自身が語るのを待たなければなりませんが、「人間力」といったものを評価に組み込むことで、表面的には明るく活発に見える生徒でも、実は評価を高めるためであって本心からの行動ではないということもあり得る。さらに、そうした自分を演じることで本音を話せる友人や理解者を作れず、心の闇を深めてしまうといった側面も無視できません。
──子どもが孤独感を深めたり、アイデンティティークライシス(自己同一性の喪失)に陥ったりしないために、周囲の大人ができることは?
大空:自己否定ループに陥らないためには、誰かに「頼る方法を知る」ということが大事です。助けを求めることは、白旗を振って他者にへりくだることではありません。社会では、懲罰的な自己責任論が蔓延していますが、他者を頼ることも自らの責任の下で行う主体的な選択の一つなのだということをわかってほしいなと思います。
■人生には色んな成功例
和田:自己責任論が強いのは、日本社会の同調圧力の強さもあるでしょう。人と違うことをするとたたかれるし、たたかれても仕方ないという考え方が、子どもにまで染みついている。当然そんなことはなくて、人は皆違うし、それでいい。それを本心から理解するには、やはり親や教師ができるだけ多くの選択肢を示してあげることです。
正直、多くの親や教師は情報に対する貪欲さが薄い。例えば、大学に行くよりもプログラミング技術を磨いたほうがいいとか、MBA(経営学修士)を取るならどこの大学院がいいとか、外国では寿司職人が年収1千万円もらっているとか、そうした情報を集めようとしません。多様な選択肢を示せず、「偏差値」というわかりやすい価値基準に飛びついてしまっている部分はあると思います。雑談でいいので、人生には色んな成功例や手段があることを日頃から話しておきたいですね。
大空:夢や目標なんて一つじゃないし、無理に探す必要もない。子どもの悩みを聞いていると、自分だけの生きる意味が欲しいけれど、見つからなくて、だから生きていても意味がないんだと自己否定に至ってしまう子がすごく多いことに気づかされます。でも人間は、意味があるから存在するわけではありません。人生は何かの目標のためにあるわけじゃなくて、自分が下した選択の連続の結果として形作られる。だから目的を達成したかどうかじゃなくて、過程にある一つ一つの選択を評価してあげたいと僕は思います。
(構成/ライター・澤田憲)
※AERA 2022年1月31日号より抜粋






































