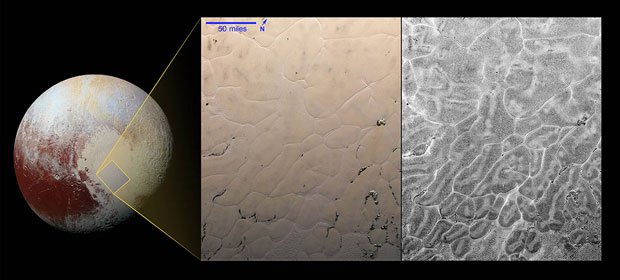
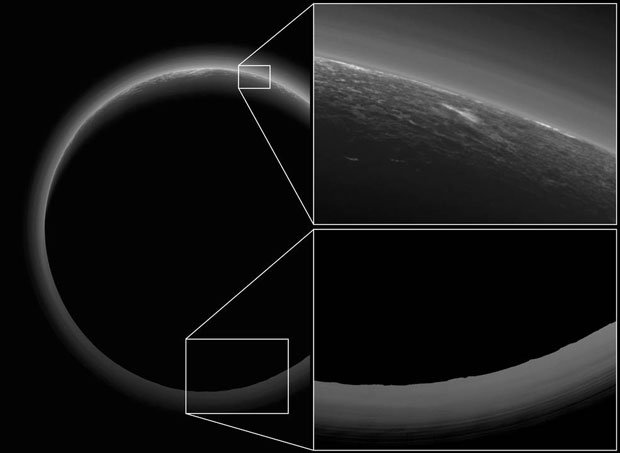
「最果ての惑星」冥王星が準惑星に分類されたのは10年前。その年に打ち上げられた米探査機が昨年7月に接近し、意外な姿を明らかにした。そのはるか彼方には地球より重い「第9惑星」の存在が予測されている。まだ見ぬ太陽系の果てへ、『最新 惑星入門』(共著、朝日新書)を著した天文学者、渡部潤一氏がご案内する。
* * *
20世紀末の技術革新は、さらにわれわれ太陽系の“地平線”を広げることになった。デジタル撮像技術、つまり半導体を用いて光を電子に変えて蓄積する素子が登場し、銀塩写真時代には見えなかった、さらに遠くの微かな天体が見えてきたのである。こうして92年、ハワイ大学のデイビッド・ジューイット氏らが、冥王星よりも遠い場所を公転する最初の小天体1992QB1を発見した。その後、同様の天体が続々と発見され、現在その数は千数百個を超えている。主に海王星の外側から、太陽からの距離が約75億キロにまで達する帯状領域に分布しており、その領域は存在を予想した天文学者の名前から、「エッジワース・カイパーベルト」(EKB)と呼ばれている。
●軌道は1千億km以遠に
ここで問題になったのが冥王星の位置づけである。実は、冥王星はEKBに含まれる天体の一つだったのだ。冥王星には仲間がたくさんいたわけである。その中では最大だったはずが、05年になって冥王星よりも大きな仲間が発見されてしまう。後にエリスと命名されるこの天体を見つけたのは、カリフォルニア工科大学のマイケル・ブラウン氏らのチームだった。
この発見が大きな契機になり、国際天文学連合は「惑星」を改めて定義し直し、惑星と小天体の間に「準惑星」という新しい分類をつくって冥王星も入れることにした。これによって、歴史的には初めて惑星の数が減ることとなった。この配置換えは、冥王星だけが見えていた時代から、その周辺領域に存在する太陽系外縁部の多くの仲間たちが見えてきた時代へ移り変わった当然の結果であった。
当時の研究者の間では、エリスや冥王星の仲間たちの発見にとどまらず、さらに多くの天体がまだ見えないながらも存在しているはずだ、という確信に変わっていく。そのきっかけは03年に発見されたセドナである。
セドナは、それまでのEKBをはるかに超え、最も内側にやってきても115億キロ、外側では1350億キロにまで遠ざかる。その公転周期は実に約1万年。大事なことは、セドナがいま最も太陽に近い場所にあることだ。つまり、これが約5千年前あるいは5千年後だったら、セドナは1千億キロよりも遠くにあって、われわれ人類が現在持つ観測技術では発見できない。太陽系の“地平線”の向こう側に、まだ未知の天体が隠れているに違いないのである。実際、セドナと同じような天体も見つかりはじめている。たとえば周期約4300年という2012VP113である。こうした発見の報告が入るたびに、天文学者は、太陽系の“地平線”がいまも広がりつつある最中であることを思い知らされる。
 渡部潤一
渡部潤一



















