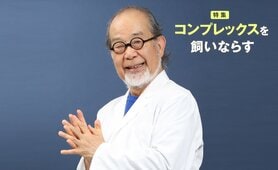温泉の泉質は主に、下記に掲げた10種類で、効能や特徴はさまざま。「炭酸水素塩泉を飲む体内の代謝や腸内細菌バランスを変化させるという実証データもあり、糖尿病予防の可能性などがあるとされます。体質や好みに合う温泉を探すことがポイントです」(野添さん)
■湯治のギモン
Q 効果は本当にある?
温泉の成分が人体に浸透し、泉質によりさまざまな効能を発揮します。周辺の自然環境や温熱効果などが複合的に作用するので、病気やケガのリハビリに温泉を利用するケースがみられます。「病気が治る温泉」として口コミで広まっているものもありますが、医学的な裏付けは乏しいです。
Q 理想的な入浴方法は?
1回の入浴は3~10分、うっすらと汗をかく程度が目安です。冬場などに体が冷えている状態で入浴すると、血圧が乱高下して入浴事故につながることがあるので、かけ湯などで体をよく温めましょう。入浴前後にはコップ1杯程度の水分補給もお忘れなく。
■真の癒やしを得たければ温泉は泉質で選べ!
※2014年に改訂された環境省の「鉱泉分析法指針」に基づく分類
【温泉の泉質と特徴】
<二酸化炭素泉>
湯屋(岐阜県)、有馬(兵庫県)、長湯(大分県)など
体に小さな気泡が付着するので「泡の湯」とも称されます。炭酸ガスが皮膚から吸収され、血行を良くする働きがあります。
<含よう素泉>
大湯(秋田県)、大手町(東京都)、聖籠(新潟県)など
2014 年改訂の「鉱泉分析法指針」で追加された泉質です。飲用で高コレステロールを改善するといいます。
<含鉄泉>
鳴子(宮城県)、天狗(長野県)、鉄輪(大分県)など
鉄分は酸化すると赤褐色になるので、「赤湯」と称されることが多いです。飲用で貧血に効くといわれます。
<酸性泉>
酸ケ湯(青森県)、草津(群馬県)、明礬(大分県)など
酸性度の高い温泉で、ピリピリとした刺激が強いです。水虫など慢性的な皮膚病に効果的です。