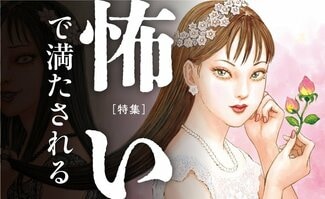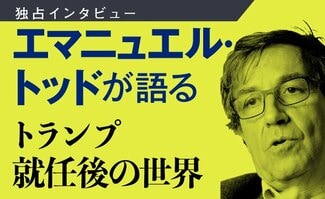練習して自己流の泳ぎを体得
ある時、息子が「これ(浮き具)がなくても泳げるようになりたい」と言い出し、夫と一緒に数日かけて練習したことがありました。
健常の次女が泳げるようになるまでには、夫が両手をつないだ状態で前に立ち、ふし浮きとバタ足の練習から始めたのですが、息子は手をつないで浮こうとすると、身体が不安定になる怖さから脇や指先に異常な力が入り、ガチガチになってしまいます。
いろいろと試した結果、夫が考えだしたのは、息子のおなかに夫の手を当てて支えることでした。
脳性まひの子どもは、手足に自分の意思とは違う力が入りやすいのですが、おなか周りは比較的柔らかいのです。夫が言うには、はじめのうちは手のひらで強く支えていたのが、慣れてくると自然に浮く瞬間が出てきたそうです。息継ぎをしようと頭を上げると身体が沈みやすいのを知り、自己流に手で水をかいてバランスを取る技も体得し、息子は泳げるようになりました。
いわゆるクロールや平泳ぎとは全く違う泳ぎ方ですが、本人は気にしていないようです。
障害児もスポーツを楽しめる
医療的ケア児の長女が通う特別支援学校にも、プールの授業があります。
温水なので、コロナ禍以前は6月から10月までプールに入っていました。
首の座らない寝たきりの子どもがプールに入るというのは、はじめは想像できませんでしたが、首の下や膝の下などに、バランスを取るための特殊な浮き具を入れると、あおむけで浮くことができます。水に浮くことで身体が軽くなるのか、いつもとても気持ち良さそうにしていました。
障害のある子どもも、少しの配慮でいろいろなスポーツを楽しむことができます。
うまくできるか?と不安に思うよりも、まずは参加して楽しめることが大切ですね。
※AERAオンライン限定記事

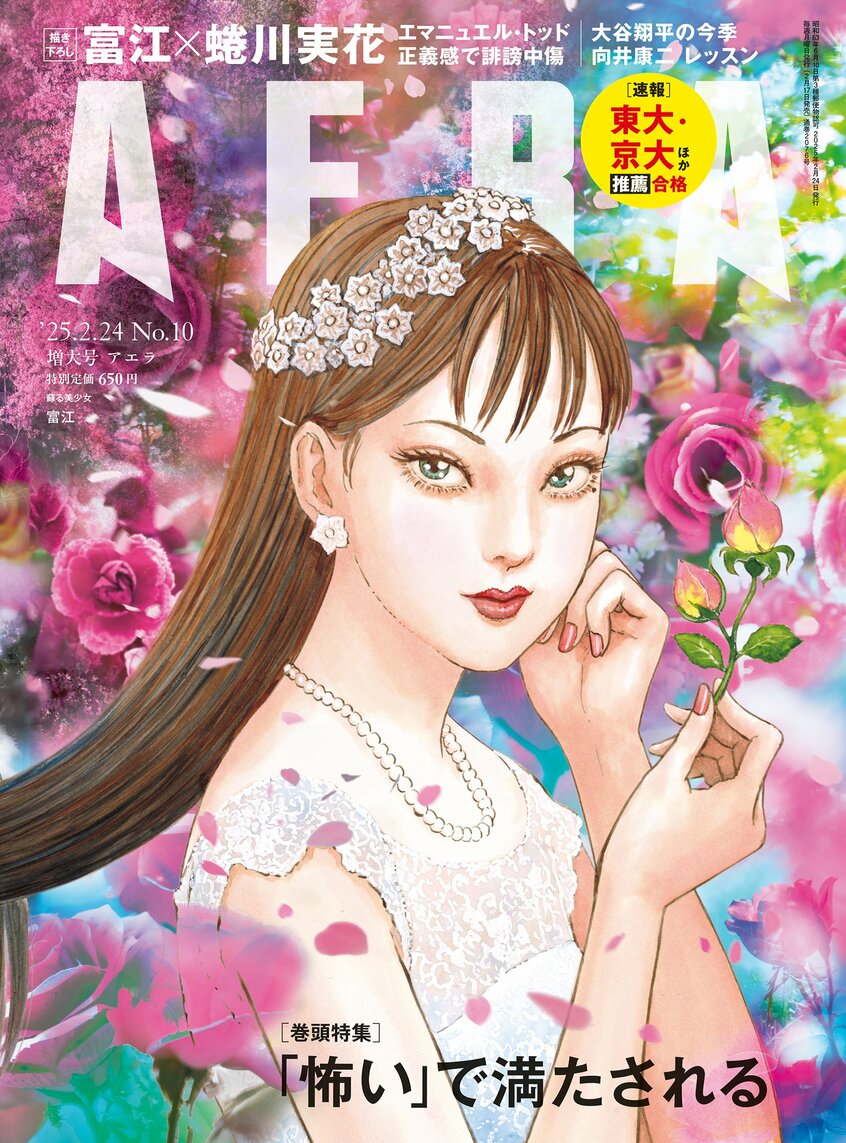
 江利川ちひろ
江利川ちひろ