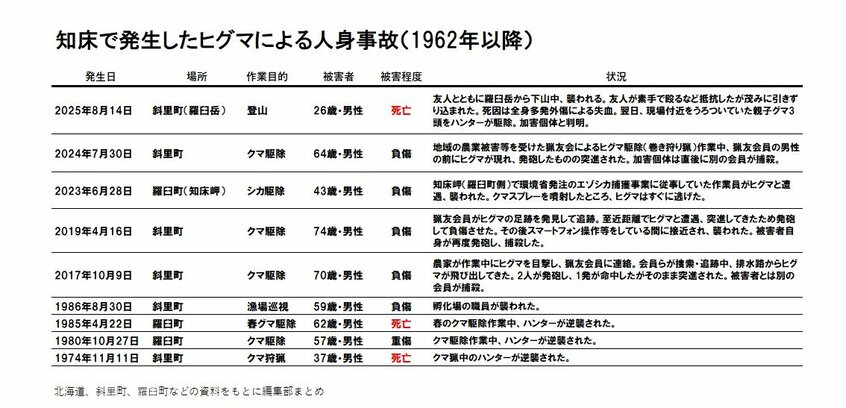
クマが人を襲うようになった「要因」
もう1点、クマの人に対する「許容度」が高いことも特徴として挙げられる。下鶴准教授はこう指摘する。
「観光客がよく来るエリアで暮らしているクマは人を見慣れています。個体差はありますが、他の地域のクマと比べると、人間と接近・遭遇してもパニックになったり、興奮して襲いかかったりしにくい個体が多いと言えると思います」
一方で、その「人慣れ」が危険行動につながる下地にもなっていた可能性も否めない。
知床を含めた北海道各地ではかつて、春先にハンターが山に分け入って見つけたヒグマを撃つ「春グマ駆除」が行われてきたが、個体数減少や保護意識の高まりから1990年に廃止された。春グマ駆除には個体数を減らすこと以外に、クマに対して人への警戒心を強く植え付ける効果があったという。
春グマ駆除が廃止され、クマの世代も入れ替わって人間への恐怖心を持たなくなったほか、2000年前後から世界自然遺産登録に向けた機運が高まり(実際の登録は05年)、観光客も増加の一途をたどった。それによりクマと人の接近・遭遇事例が増え、クマを見るために一時停止する車が連なる「クマ渋滞」も、シーズン中は連日のように発生している。
下鶴准教授は続ける。
「知床に観光に来た方がクマを見かけて車をいったん止めるのは自然なことだと思います。ただ、クマにしてみると連日それが続き、少しずつ距離感がおかしくなってしまう可能性はあるでしょう。また、中には必要以上に接近したり、クマにえさを与えたりするモラルのない観光客もいて、ずっと問題視されてきました。22年に改正自然公園法が施行されたことで、これらは明確に違法行為になりましたが、なくなっていません」
ヒグマなどの野生動物が人間から与えられた食べ物や、人間が放置した食べ物を食べると、動物は同じ味を求めて再び同じ場所に現れたり、人間に付きまとったり、場合によっては人間を襲うなどの行動をとりやすい。



































