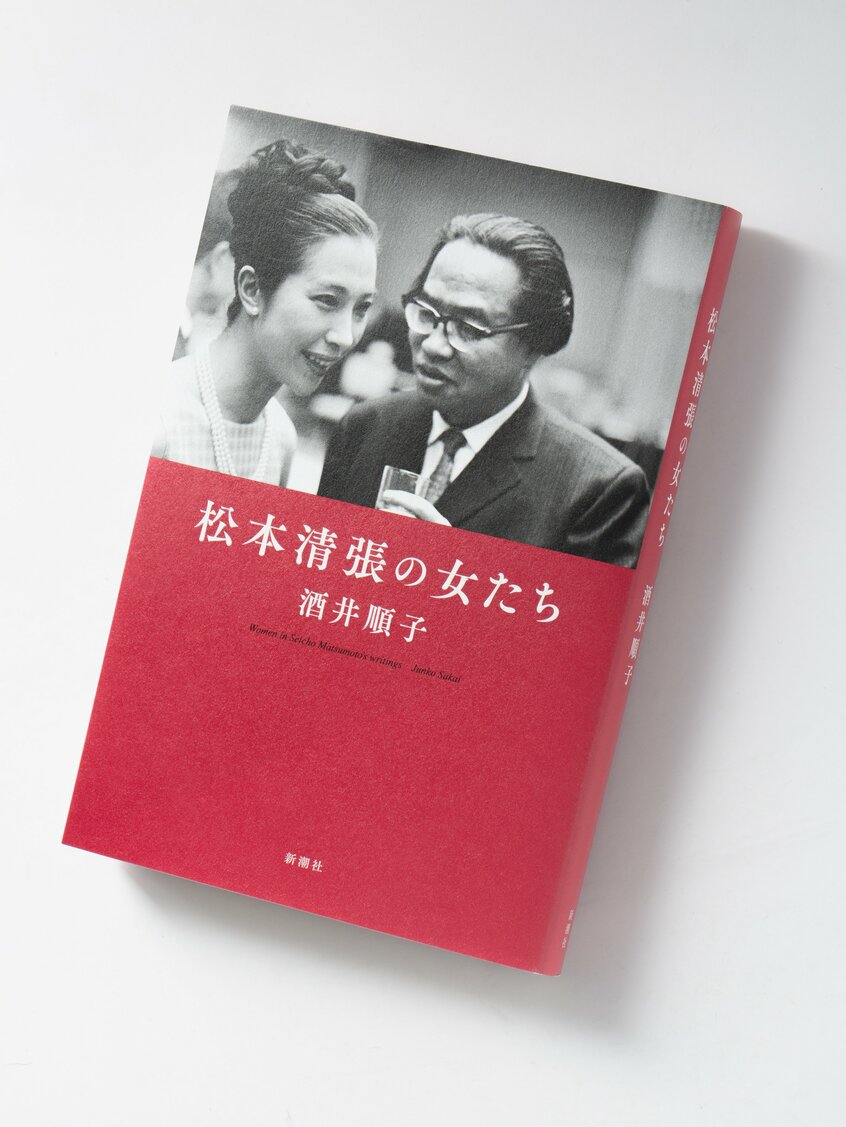
女性の存在感が強い清張作品と言えば『黒革の手帖』のような悪女ものが浮かぶが、実は酒井さんが〈お嬢さん探偵〉と命名する、素人探偵が活躍する作品群も多いのだ。
「女子大出だったり高キャリアだったり、当時の女性読者が我が身を重ねやすい部分もありながら、ちょっと憧れを抱くことができるような人物を探偵役に据え、女性たちを推理小説の世界へ誘ったわけです。女性誌で多く登場させた〈殺す女〉同様、〈お嬢さん探偵〉も“清張と女性”を考える上では、重要な存在なのではないかと思いました」
取材を始める前と後で清張に対する印象でもっとも変わったのは、昭和を生きた男性なのに女性をフラットに、人間として捉えていた知的な視線の持ち主だったことだという。
「女性の役割みたいなものが女性にまだ押し付けられていた時代に、女性を男性と同等の欲望を持つ存在として描いたのが清張。誰もが持っている黒い部分やえげつない欲望を、彼が小説の中に落とし込んでくれたから、読者自身は悪事を働くことなく欲望を浄化させることができた。そういう一種の消化剤的な役割もあったのかもしれません。現代にも通じる感覚だからこそ、清張作品は読み継がれているのかなと思いますね」
(ライター・三浦天紗子)
※AERA 2025年7月28日号
こちらの記事もおすすめ 直木賞候補作『踊りつかれて』 塩田武士が描く情報化社会の闇「小説はここまでできる」







































