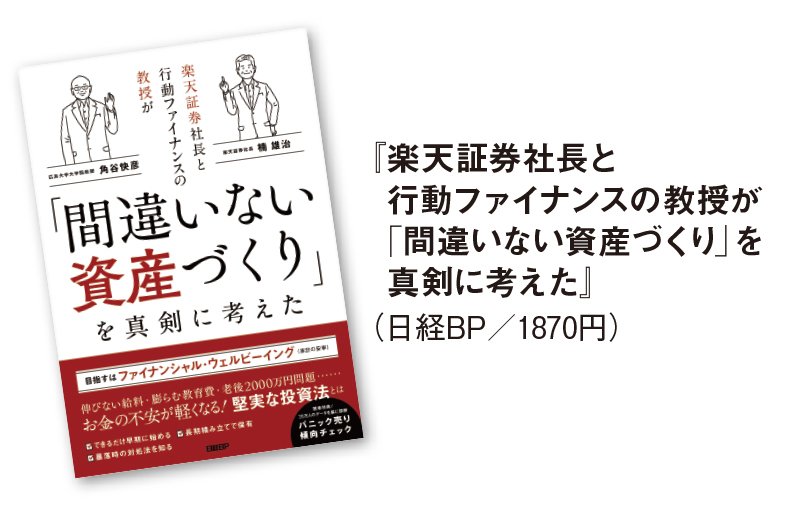
ノーリスク10%時代
その後の高度成長期は高金利時代。1970年代の2度のオイルショックで日本の政策金利(公定歩合)は9%に。80年代のバブルでも長期金利は上昇した。利付金融債の一種である「ワイド」や信託銀行の貸付信託の一種「ビッグ」の利回りは10%近くになり、発売日には支店の前に長蛇の列。ほぼノーリスクで年10%近い利息がもらえるなら、誰もリスクのある投資などしない。このような高金利時代が成功体験となり、日本人に預貯金信仰が根付いた。
投資を敬遠して預貯金に執着するのは日本人のDNAのようなイメージもあったが、そうではなかった。「預貯金信仰」は国が作った側面が大きい。洗脳というのは言い過ぎだろうか。
「高度成長期には銀行で集めた預金を産業振興のための融資に回していました。戦後の立ち直りの過程において、そうせざるをえない背景があったわけです。昭和時代のモデルが一般の人たちの頭にこびりつき、国のあり方も長らく変えられなかった。一部の地方銀行が目下、高い金利を提示して預金を集めていますが、集めた預金の貸出先はあるのか心配になります」
税金に疎い会社員
税金についても興味深い考察が書かれている。見出しは「税金のことを考えなくても生活できる日本」。まさに。
日本で会社員として働いていると、自分の収入や支出はわかっても、どういう計算で税金が決まっているのか細かくチェックできる人は少ない。その理由の一つが日本の納税制度。日本の会社員は所得税を自分で納めることなく、勤務先が給与から天引き(源泉徴収)してくれる。年末にその年の収入が確定した時点で、本来納めるべき所得税と照らして差額を戻す「年末調整」まで勤務先がやってくれる。投資の税金にしても、証券会社で「特定口座(源泉徴収あり)」を選べば値上がり益や配当にかかる税金を証券会社が計算して勝手に納めてくれる。
つまり一部の例外を除けば日本の会社員は確定申告をする必要がない。これでは税金を学ぶ機会など生まれない。米国やフランスなどの会社員は、自分で確定申告をして納税をする。日常的に「どの税理士がいいか」「このスーツは経費で落とせるか」などの会話をするという。





































