一方で、これまでのように寺院側が出向いて布教活動をすることはなくなっていった。国民を強制的に寺に帰属させる檀家制度は、仏教が江戸幕府の公認を得たことを意味する。なかには、その立場にあぐらをかき、布教や修行を怠る僧侶も現れた。
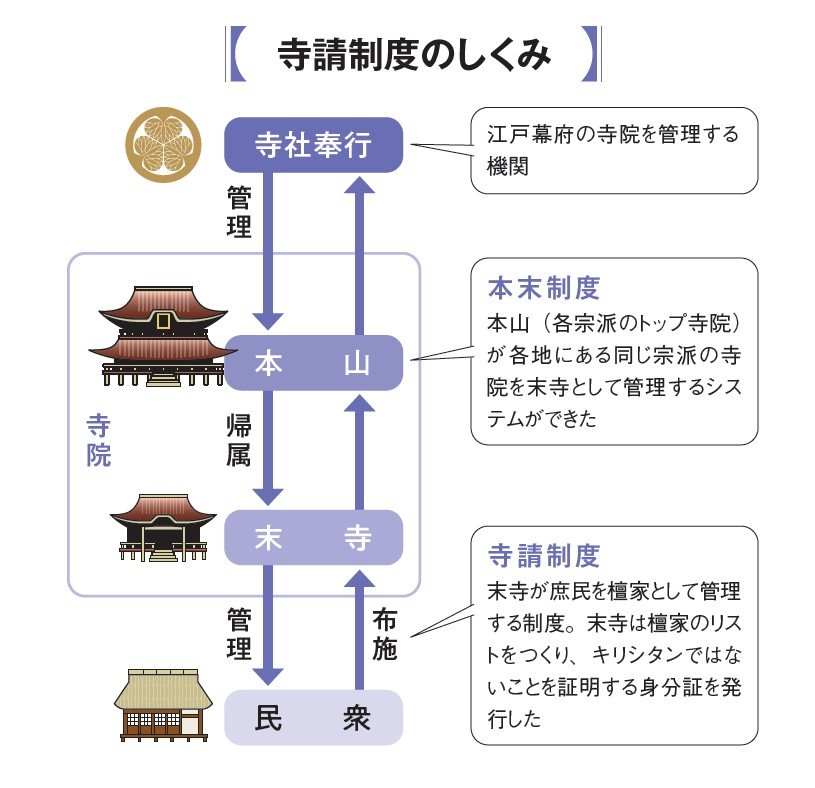
現代に残る伝統もこの時期につくられる。それが仏式の葬儀だ。江戸時代より前、仏式の葬儀は貴族や皇族など、限られた人々だけのものだった。しかし寺院が戸籍を管理するため、寺院は自分の檀家の出生・死去を把握するようになる。その流れで僧侶が呼ばれてお経を唱えるという、今と同じ葬儀のスタイルができあがっていった。
お盆は、仏教行事「盂蘭(うら)盆」の略語と言われており、日本古来の信仰と仏教が結びついた先祖供養の儀式だ。最初に盂蘭盆が行われたと言われる推古天皇の時代には朝廷の儀式だったが、鎌倉時代に民衆に広まり、江戸時代になると、僧侶が檀家の家々を巡って読経するようになったという。
(構成/生活・文化編集部 塩澤巧)
こちらの記事もおすすめ もし弔辞を頼まれたら……「断っていい?」「内容は?」知っておきたい弔辞の基本





































