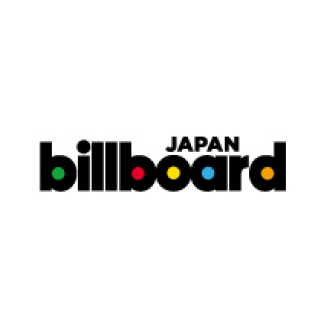『タイピスト!』(2012年)のレジス・ロワンサル監督が手掛けるミステリー仏映画『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』が2020年1月24日より劇場公開する。全世界待望のミステリー小説の世界同時出版のため、完全隔離された密室に9か国の翻訳家が集められるが、ある夜、冒頭の10ページがネットに公開。出版社社長の元に「24時間以内に500万ユーロを支払わなければ、次の100ページも公開する。要求を拒めば、全ページを流出させる」という脅迫メールが届く。
トム・ハンクス主演で映画化された『ダ・ヴィンチ・コード』シリーズの4作目『インフェルノ』の出版時に、著者ダン・ブラウンの同意のもと、違法流出を防ぐため、各国の翻訳家たちが地下室に隔離され翻訳を行っていたことが報じられたが、本作はそのエピソードをもとにしている。デジタル時代ならではの仕掛けがちりばめられた本作のラストに驚愕することだろう。今回、本作の音楽を手掛けた世界的音楽家・三宅純に話を聞いた。
――この作品の音楽を手がけることになった経緯を詳しく教えてください。
三宅純:この映画のミュージックスーパーバイザーをしているエマニエル・フェリエが、僕に提案してくれた作品のひとつが、この『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』でした。まず英語の脚本を読ませていただいたんですけど、とても入り組んだ複雑なプロットになっていたので、これをどう映像化するのかという点に興味を惹かれたのが最初です。
――レジス・ロワンサル監督の約7年ぶりの作品になりますが、監督にはどのような印象をお持ちでしたか?
三宅:レジス監督の前作である映画『タイピスト!』は拝見していました。脚本を読ませていただいた際に、本作のイメージ写真も一緒に拝見したんですが、それを見る限り『タイピスト!』のようにスタイリッシュでキッチュな作風になりそうで、今回のサスペンスとどう合体していくのか、想像が付かなかったんです。だからこそ、おもしろい作品になるのではないかと。レジス監督に会ったときも、僕にも馴染み深いジャズやギル・エヴァンスが好きというお話もされていたので、組み易いのではという印象を受けました。
――三宅さんはどのように楽曲制作を進められますか?
三宅:映画の場合、基本的には完成に近い映像素材を手に入れてから音楽を作り始めます。フレーム単位で映像に音を合わせたり、会話を縫うように音楽を作り上げていったりすることになるので、映像が完成形に近いことが必須条件です。少しでも、映像の構成が変わってしまうとカスタムメイドした音楽が機能しなくなってしまいますから。ただ、今回は結果的に、通常のプロセスとは真逆の方法で制作を進めることになりました。というのも、映画作りを進める中で、レジス監督をはじめ、エディターや製作陣に迷いが多く生じていたようで、その度に変更される内容にあわせて曲を作り変えて行くことになってしまったのです。映像が変われば、当然、求められる音楽も変わってきますから、今までで一番ハードな仕事になりました。最終的に完成した作品は、僕が最初に観た映像とはまったく別物に仕上がっています。ただ、音としての仕上がりは気に入っていますし、映画音楽らしいものが出来上がったと思っています。
――あるシーンでは、嫌らしい時計のチクタク音がバックに使われていて、観客の緊張感を煽る感じがしました。これは時間が迫っているという演出でしょうか?
三宅:あのシーンは、電車の時間や車両ナンバーなど、時間や数字に紐付いた作りになっているので、レジス監督から時間の刻みを感じるような要素を入れてほしいというオファーがありました。クラベスという打楽器を、サンプリングした時計の音に被せる形で使っています。セリフと映像を観ながら、そこに何が足りなくて、何を足すともっとドラマの効果が上がるのか、この会話だけは音楽とぶつからないように、といったことを構想しながら作っていきました。楽器選定や曲作りそのものに関してはインスピレーションを大切にしています。
――バート・バカラック作曲の「世界は愛を求めている(原題:What The World Needs Now Is Love)」が映画の中でもキーとなる要素ですが、この曲と関連する楽曲はございますか?
三宅:この曲自体は映画の中で独立して描かれる1曲だと思っているので、特に関連付けて音楽を制作していません。でも、実はいくつかあった候補曲の中から「What The World Needs Now Is Love」をチョイスしたのは僕なんです。単にバカラックが好きだから、というだけなのですが、実際にこの曲になって良かったです。
――映画音楽は観客の集中を邪魔させない、そして音楽でそのシーンを補足するという重要な役を担っていますが、そういった劇中音楽を作る上で、三宅さんが大切にしているルールはありますか?
三宅:自分自身の作品を作るときは音楽を主体で考えますし、そういったものを作りたいと思って音楽家になったわけですが、映画の場合は、主体が映像とセリフと演技にあるので、そのためのスペースを空けることに気を付けています。こだわりを持たないことにこだわるというか、一本骨を抜くという作業が映画音楽として大事なことではないかな、と思っています。ダンス音楽も同様ですよね。主体となるものの気持ちを音楽ですべて語ってしまっては、やり過ぎになってしまう。音楽から主旋律を抜いてしまうということも有り得ますし、それを前提に曲作りを考えていかなければならないので、音楽家にとって「映画音楽の制作」という仕事が良いのか悪いのか、分からない場合もあるんです。それでも映画音楽を作っているのは、僕自身、映画というものを愛してるからです。それに、音楽の機能をとても認識できる仕事だと思っています。音によって映像の見え方は全然違うものになるので、それを体験、実感しつつ、自分だったら何ができるだろう、というチャレンジになっているんです。
――ちなみに、三宅さんはどのような映画音楽に惹かれますか?
三宅:フェデリコ・フェリーニにとってのニーノ・ロータやアルフレッド・ヒッチコックにとってのバーナード・ハーマン、デヴィッド・リンチにとってのアンジェロ・バダラメンティなど、少しキャラがたっている人が好きです。この映画にはこのサウンド、という刻印が押してあるようなものが好みですね。先ほどお伝えしたような「一本骨を抜く」と言ったものとは逆の作風なのですが……。ニーノ・ロータは、フェリーニが映像を撮る前に音楽を作らせてくれ、と言っていたらしいです。その上で完成した音楽を自由に編集して使ってくれ、と。バーナード・ハーマンもヒッチコック作品に対して、それに近いことを要求したこともあるようなんですよね。今の時代、それを許してくれる監督も少ないかもしれませんが、この手法だからこそ音楽に主体性が生まれ、逆にその力を借りて映画が完成しているような気がします。今後そういう作品に関われたら素敵だなぁと思っています。
――最近は音楽ソフトや機材がすぐ手に入り、サブスクで世界中の音楽が簡単に聞けるようになりました。日本の学生やプレイヤーが海外で勉強をしなくても高いレベルの作品を作れる環境が揃ってきていると思いますが、こうした近年の音楽的な動きを、第一線で活躍されている三宅さんからみて、どう感じますか? これまでのご自身の経験と比べてみると、世界は近くなったと思いますか?
三宅:例えばLP時代の、片面を一生懸命聞いて、裏返してまた曲を聞く、といったことをしなくなりましたよね。簡単に音楽を聞けることによって、音楽そのものの存在感が薄れているようにも感じています。やっぱり、いい音楽は向き合って聞くべきじゃないかと思うのです。音質的にも圧縮された音は耳にも神経にも良くないですし。ただ、技術が進歩したことの便利さや、世界との距離感は近くなったと感じています。昔は、空港のX線を避けるために大きなマルチトラックテープをアルミホイルで巻いて運んだりと、色々苦労をしていました。今は小さなハードディスクに全部入ってしまうし、便利にはなりました。でも、不思議なことに、デジタル機器にアナログ時代に良かったもののシミュレーション(模造品)をプラグインでたくさん付けているんですよね。「だったらアナログのままでいいのでは?」とも思ってしまいます。自分自身もデジタル機器を使っているので難しいところです。
Photo by Jean-Paul Goude
◎公開情報
『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』
2020年1月24日(金)より、全国ロードショー
監督・脚本:レジス・ロワンサル
音楽:三宅純
出演:ランベール・ウィルソン、オルガ・キュリレンコ、アレックス・ロウザーほか
配給:ギャガ
(C)(2019) TRESOR FILMS – FRANCE 2 CINEMA - MARS FILMS- WILD BUNCH – LES PRODUCTIONS DU TRESOR - ARTEMIS PRODUCTIONS
◎リリース情報
映画『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』オリジナル・サウンドトラック
2020/1/24 RELEASE
PCD-24911 2,400円(tax out.)