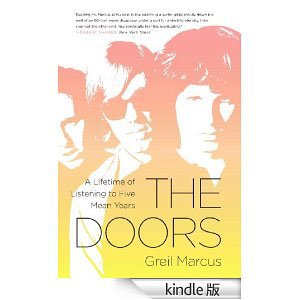
■ドアーズの知られざる音楽史
著者グリール・マーカスは、ドアーズのファースト・アルバムがリリースされた時からのファンであり、伝説的なフィルモア・オーディトリアム(サンフランシスコ)や1967年のアヴァロン・ボールルームにおいて、幾度となくバンドのパフォーマンスを目の当たりにした。
だが、5年後にすべてが終わった。ヴォーカリスト、ジム・モリソンが、パリで死体となって発見され、バンドが解散したからだ。
マーカスはその40年後に、時計の針を戻し、FMポップ・ステーションのチャンネルを次々に変えて、1時間の間にドアーズの曲を立て続けに聴くことができるような、探求の旅へと誘う。
音楽における需要が何であれ、彼らは、常に飽き足りなさを感じ、きわめて大きな意味で、決して終わらず、絶対的に生き続けている。
ドアーズに関する書籍は、これまでに数々出版された。だが本書は、ドアーズの神話や神秘性、ジム・モリソンの死生観や彼を象徴化した時代を初めて度外視し、彼らの音楽のみに焦点を当てたものである。
■第2章≪ミステリー・トレイン≫より
1970年5月2日、ピッツバーグのステージにおいて、≪ロードハウス・ブルース≫の演奏が、7分にわたり延々と繰り広げられた。まるでコルヴェットが、スムースな変速ぶりを単に誇示するためだけに、何度も5速にギアチェンジを行なうかのように。
ドアーズが演奏を中断し、ジム・モリソンは一息ついた。彼は、≪ピープル・ゲット・レディ≫を、低くつぶやくように歌いはじめ、インプレッションズのメッセージを、ナイトクラブの同胞に対する賛歌として掲げた。
“People get ready/For that train to glory。”
だがそれは、グループが乗り込もうとする列車ではなかった。
優に3分以上の間、ギターはスクラッチ・ノイズを立て、蒸気機関車がガタゴトと進むようなペースでリズムを刻み、オルガンは、車窓の景色が移り変わるような速度でキーを叩いた。≪ミステリー・トレイン≫は、そうして展開し、ジム・モリソンが飛び込む下地を作った。彼はまさに、絶妙のタイミングで加わった。だが、その演奏は、彼を必要としなかった。つまりそれは、レイドバックした、独自のスタイルをなしていた。
モリソンは、少しの間、歌った。リズムが、彼の粗野で締りのない声や発音の不明瞭な言葉を、すべて補った。彼はその後、バンドに曲を託し、もう一度加わると、再び演奏を投げ捨てた。
≪ミステリー・トレイン≫は、なおも続いた。そして演奏は、≪アウェイ・イン・インディア≫、≪クロスローズ・ブルース≫という新たな曲を交えつつ、10分、12分、ついには15分前後に及んだ。だがそれは、まったく一体化した演奏であり、どこかに到達しようとする、あるいは出発しようとし、境界線を越えようとする一つの試み、一つの曲になっていた。
演奏時間が、7分に差しかかると、曲が、自らの意思を持ちはじめたように思われた。つまり、曲自体の想念を聴きとることができた。たとえば、車輪が線路を意識し、蒸気機関は、線路に接する車輪や車軸の正確な連動性に驚くというように。
モリソンが演奏に戻ると同時に、そのすべてが消え失せた。バンドが再び、最初のリズム、あのスクラッチにどうにか辿りつくと、モリソンがまたしても、ブルース・ソングのエレメンツを放り棄て、演奏を単調なものにした。彼は、それらをまったく顧みず、ヴォーカルをとった。
ブルース・ラインは、メロディーからピックアップする場合、エンドレスに続くものである。それらは使用済みの乗車券に過ぎないが、その価値が下がることは、決してない。(抜粋)[次回11/17(月)更新予定]
































