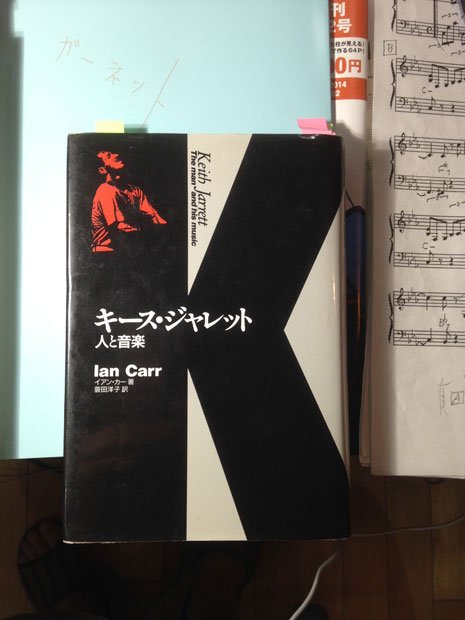
『キース・ジャレット―人と音楽』イアン カー著/蓑田洋子訳
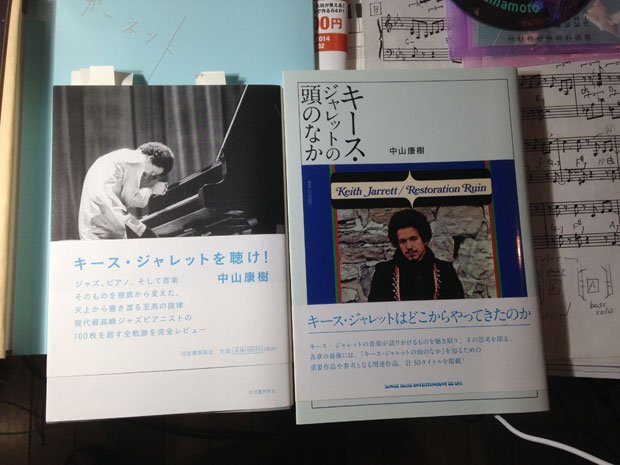
『キース・ジャレットを聴け! 』中山康樹著
『キース・ジャレットの頭のなか』中山康樹著
昔、確かグレン・グールドのインタビューだったと思うのだけど「生まれたばかりの赤ん坊を人里離れた山の中にさらっていって、難解な現代音楽ばかり聴かせて育てたら、その子は普通のドレミのメロディーに無反応で、先鋭的な音を喜ぶ子に育つと思うかい?」という場面があって、こいつなんて残酷なことを訊くのだろう、と絶句したのを覚えている。
「難解なって言うけど、音楽って結局はその音を感じるか感じないか、なんじゃないの?」ということが巷間でよく言われているが、実はちゃんと難解な音楽というものは存在し、でも「難解な音の連なりがわかりやすく聞こえてくるようにする訓練」というものもあるのです。
グールドもそのことを言いたかったのだと思うし、ちゃきちゃきのディープ・パープル小僧だった私が、一念発起してジャズ学校に入りバップばかり浴びるように聞かされて「おーまいごっど、こいつら何弾いてんねん(謎)」と当初はかのウイントン“ハッピー”ケリー様ですら難解だったのだが、いつの間にか「ふっ ケリーはもう卒業、やっぱキースだね」というスノッブな阿呆に変身してしまうのだ(皆様はしてしまわないでください(T_T)
で、ジャレット様。先日も大阪で一悶着あったらしいが「彼は聴衆を一連の作曲された曲の受動的な受け取り手と考えるのではなく、その時そこで起こりつつある音楽創造のプロセスの能動的な立会人、参加者として考えているのである」(『キース・ジャレット 人と音楽』 イアン・カー著 簑田洋子訳より)
すべてがここに集約されています。が、ですが! はっきり言って最近「能動的な立会人=本物の愛のあるリスナー」が少ない。みんな「受動的な受け取り手」に成り下がっている。と、お前なぞが何をエラそうに言う、はい、そのとおり(^_^; ですが、これくらい大上段からモノ申して、喝!(by大澤親分)を入れないとだめになるくらいライヴシーンは「軽佻浮薄なお約束=定番演目のこれやっときゃいいよね的再現」に満ちあふれている。もう一度、演者を生かすも殺すも聴衆だということに基本に立ち返って「アーティスト応援」の意味を考え直そうよ!
あれっ? 全然ほめちぎってない(大汗)まあそういう回もあるということでお許しを。定番演目? うん、これから書きます。うちのオヤジをだしにして(^^)
俊太郎の定番と言えば『生きる』「生きているということ いま生きているということ……」で始まる有名な詩だ。たしかにいい詩だと思うのだが、震災以降「絆」という単語同様に、誰もがよってたかってこの詩を凡庸にしてしまった感が拭えない。私は『がっこう』という詩をニヤッとしながら学校で朗読する俊太郎のファンだ。「がっこうがもえている きょうしつのまどから どすぐろいけむりがふきだしている……」パンクだ! 挑発だ!! キース(の調子の良い時)だ!!! この詩を彼が読んでいると、生徒たちは黙ってうつむいてもじもじ。先生方は「まあ、谷川先生お戯れを」と戸惑いのひきつった微笑。それを見ながら「どうよ、詩ってほんとはこうでなきゃ! 詩はJAZZなんよ」とほくそ笑む私も偽悪的な奴だが、この気持ちのよいカンフル剤が世界のもう片方にある、と認めないと「生きる」もくそもないでしょ、と私は思うのですが、どうでしょう?
本人からきいたのだけど、この詩をUSAのどこぞで朗読したら「生徒たちは全員拍手喝采、指笛ピューピュー。先生たちは「F◯C◯!」という怒りの顔で俺を睨んでた」とのこと。ああ。芸能の発信ー受信の基本からして、すでにあちゃらさんに負けてるのかいのう(ため息)。こりゃあサッカーどころじゃあらへんで(^_^;
おまけの一言。だからキース『The Melody At Night With You』は、ぬるいよ。いくら病み上がりとはいえ、こういうの出すからみんな勘違いするんじゃないか![次回7/28(月)更新予定]
































