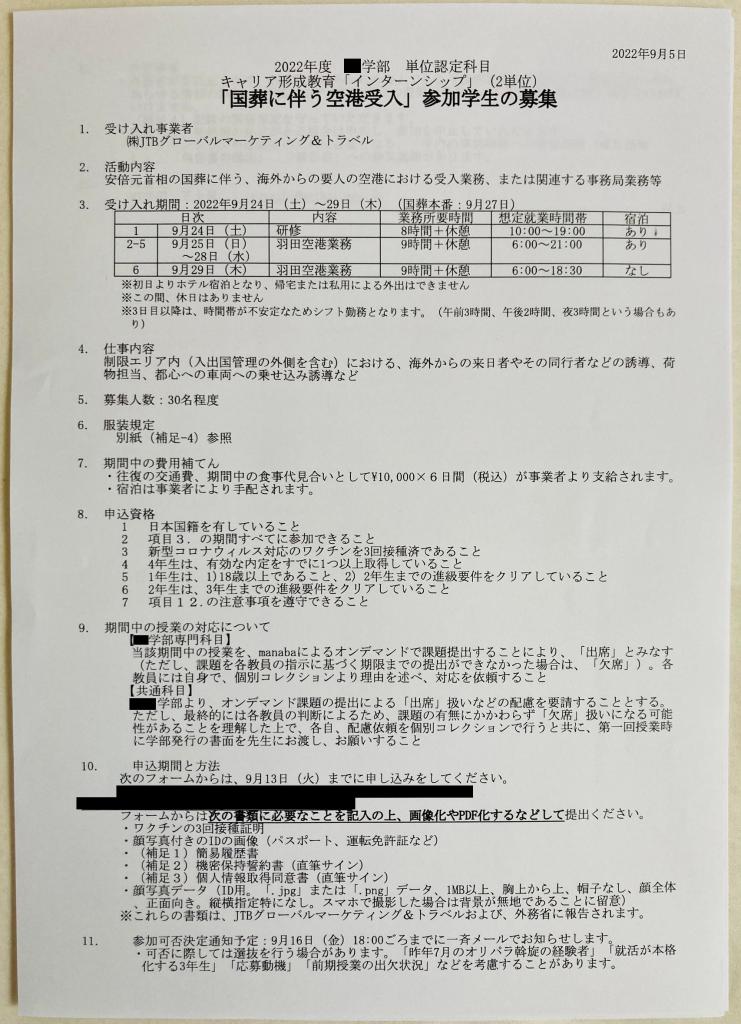
「本来、学生の出欠や単位付与を決めるのは、大学ではなく教員です。こうした要請は、教員への無言の圧力となり、大学の方針に従わざるを得ないでしょう。もし欠席扱いにしたら、その教員は大学からも学生からも避けられてしまう。教員にとっては教育活動の侵害ともいえる要請だと思います」
そもそも、大学が国葬という世論を二分している国家的行事に、単位取得を前提にして学生の労働力を提供するという姿勢は「学問の府」として正しいのか。小林さんはこう指摘する。
「大学は国からの助成金をもらったり、認可を受けたりしている立場上、基本的に“お上”の言うことは聞かざるを得ないと受けてとめてしまう。世論が割れている行事で人材を集めるなど、学問の府として国から独立すべき大学が、国の下請け機関になりかねない。これでは、大学の自治も学問の自由も失われてしまいます」
もちろん、外国人相手の接客や接遇を学びたい学生からすれば、就職希望の事業者からインターンシップ募集があれば、参加したい気持ちになるだろう。
だが、そうした学生の意欲が政治的に利用されてはならない。大学側は、その点にもっと注意を払うべきではなかったか。
「国葬は、オリンピックと同様に国家の一大行事です。世論を二分するその国家的行事に、学生を参画させることで、大学の単位を認めてしまうことは、本来あってはならないことだと思います」(小林さん)
あらゆるところで禍根を残す「国葬」となってしまった。(AERA dot.編集部 岩下明日香)





































