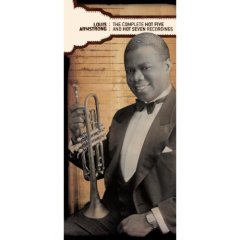
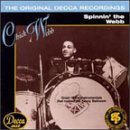
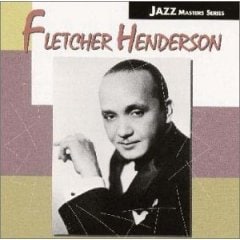
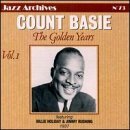
●ジャズ・ドラムス前史
ジャズのオリジナル楽器
ジャズはニューオリンズのブラスバンドを母体とする。管楽器はそこから、ピアノはラグライムから、弦楽器は民族音楽とクラシックから持ちこまれた。ドラムス(ドラム・セット)だけはジャズを起源とする。構成する打楽器はブラス・バンド伝来だが、重要なセット化はジャズ界で進んだ。シンバルのバス・ドラムへの取り付けは軍楽隊が先行したが、バス・ドラムを踏み鳴らし、シンバルを打ち合わせるペダルはジャズ界が生み出した。タムタム、フロア・タム、シンバルを増設し、基本セットを完成させたのもジャズ界だ。
ジャズを特徴づけるのは躍動的なリズムにほかなるまい。それを送り出すのがドラムスの役割だ。ドラマーの影響を語るには、どの打楽器がどう叩かれているかを知ることが必須だが、初期は往生する。昔のことで音質が良くない? それもあるが、それ以前の話がある。20年代の終わりまで、スネアとシンバル以外はスタジオへの持ち込みを禁じられていた(注1)のだ。20年代の演奏を聴くと、ドラムスに奇異な感じを抱く。聴こえるのはウッド・ブロックとシンバルだけ、これではドラマーではなくてパーカッショニストだ。
録音技術という大きな壁
20年代の終わりにバス・ドラムの持ち込みは解禁されたが、聴きとれないことでは無いも同然だ。ドラムスはジャズを起源とするだけに奏法は飛躍的に発展したが、音で追うのは難しい。ほとんど音が聴こえないときては、影響の在り方もほかの楽器とは異なってくる。レコードは役に立たず、実演に接して学ぶか、教えを受けるしかない。われわれが初期のドラマーについて多くを知らないのは、録音がないのではなく、そもそも広範な影響を及ぼすことができなかったから、ジャズ史の上で語りようがなかったからではないか。
30年代の後半に高忠実度マイクが実用化され、どうにか聴きとれる打楽器の数が少しは増えるが、フル・セットが聴こえるようになるのはバップ期になってからだ。初期のジャズ・ドラムスの大物について、そのスタイル形成を知る術はなきに等しい。まがりなりにも検証に耐えうるのは、既に名をあげた、初期のスタイルが出来あがってからの録音だ。影響源を推し量るには、完成したスタイルに先人の痕跡を探すほかないのだ。今回とりあげる巨人もその例にもれない。録音技術という壁はファンの前にも立ちはだかっている。
ホット・ジャズ期の大物
史上初のジャズ録音は白人グループ、オリジナル・ディキシーランド・ジャズ・バンドの《リバリー・ステイブル・ブルース》だ。奇跡的にドラムスの音がよくとらえられていて、バス・ドラムの強打すら聴こえる。これなら手本になる。トニー・スバーバロは広範な影響を及ぼせた初のドラマーかもしれない。より重要なのは後続の白人バンド、ニューオリンズ・リズム・キングスだ。ベン・ポラックにはニューオリンズ派のドラマーにはない2拍目と4拍目の強調が見られる。黒人が創造し白人が模倣するという俗説が揺らぐ。
20年代の後半、シカゴで活躍したニューオリンズ派の大物にベイビー・ドッズとズッティ・シングルトンがいる。ドッズはソック・シンバル(ハイハットの前身)の開発者とされるが、実際は助言者で、そもそもシンバルに関心はなかったと語っている。パワフルでワイルド、ウォッシュボード(注2)を使った演奏も少なくなく、ニューオリンズの伝統に忠実だったといえそうだ。ズッティは洗練され、新しい奏法への取り組みも積極的だった。ともに影響力はシカゴ周辺にとどまったが、度合いはズッティが勝っていると思う。
同じ頃のシカゴで、黒人の演奏に魅せられ、ジャズを演奏し始めた白人の若者たちがいる。そこから現れた大物がジーン・クルーパとデイヴ・タフだ。彼らは白人ドラマーの流れをくみつつ、ドッズやズッティの奏法も習得した。クルーパは初めてフル・セットで録音し、ドラム・ソロを創始する偉業を成し遂げたが、本質は最高のディキシーランド・ドラマーというべきで、影響もそのあたりにとどまった。より重要なのは、ジョー・ジョーンズ(後述)とならんで近代ドラミングを創り出したタフだ。シェリー・マン、ジョー・モレロ、ドン・ラモンド、メル・ルイスといった白人ドラマーはタフの系譜につらなる。
注1:当時の録音は、壁に設けた朝顔状の集音器に音を吹き込み、振動エネルギーのかたちで針に伝え、ワックス盤に溝を刻むというものだ。中低音打楽器の一撃は機器に障害を及ぼすということで使用を禁止された。20年代の半ばにマイクが普及しても記録の仕組みは同じだったから、クルーパの無謀な試みが功を奏するまで解禁されることはなかった。
注2:洗濯板。表面に薄い金属板を貼り付け、両手指先にはめた指貫などでカキ鳴らす。
●チック・ウェッブ(1909‐1939)
ジャズ・ドラミングの創始者
今日につらなるジャズ・ドラミングを創始したのはチック・ウェッブだ。ドラムスの地位をメトロノームもどきから音楽の活性剤・起爆剤に押しあげ、新時代を切り開いた。ドラム・セットの基本形となる、各種の打楽器を統合したのもウェッブだとされる。生まれつきセムシで小人だったが、旺盛な闘争心によって逆境をはねのけ、スウィング期を代表するバンド・リーダーとして30年代を通じてハーレムに君臨した。しかし、貧弱な録音の壁にはばまれ、スタイル形成はもとより、その偉業すら満足な形で知ることはできない。
メリーランド州ボルチモア生まれ。上記のハンデに加え、3歳頃に階段から転落、半身不随も同然となる。リハビリにドラムスを勧められ、9歳で最初のドラム・セットを手に入れた。12歳でプロ入り、25年にニューヨークに進出、ジャム・セッションで腕を磨く。26年にはジョニー・ホッジス(アルト)を擁したグループを結成し、27年1月からサヴォイ・ボールルームに出演する。その後のバンド経営は順調とはいかなかったが、30年にサヴォイに復帰、30年代半ばに絶頂期を迎え“キング・オブ・ザ・サヴォイ”と呼ばれた。
リズムの化身でジャズ合戦狂
サヴォイの呼び物はジャズ合戦だった。ウェッブは去来する対バンドに挑み、クルーパを擁した絶頂期のベニー・グッドマン楽団ですら苦杯を喫する。こうした武勇伝を当時の録音から思い浮かべることは難しい。29年から35年まで、どうにか聴こえるのはシンバルの一撃とブラシで、腕前はバンドの躍動感から推して知るべしといった按配なのだ。36年、ようやくドラム・セットらしい音に近づく。37年11月の《ハーレム・コンゴ》と38年5月の《ライザ》のパワフルでカラフルな妙技を聴けば、少しは凄腕が実感できるだろう。
ジャズ・ドラムス史はウェッブ以前と以後とに画される。スウィング期のドラマーは例外なくウェッブをモデルとした。自らも影響源となった大物をあげておく。黒人ではシド・カトレット、ジョー・ジョーンズ、ケニー・クラーク、アート・ブレイキーがいて、これがジャズ・ドラムスの主流をなしている。白人ではクルーパ、タフ、バディ・リッチ、ルイ・ベルソンがいて、こちらは白人ビッグ・バンド・ドラミングの主流をなしている。
●シド・カトレット(1910‐1951)
ジャズ・ドラマーの鑑
“ビッグ・シド”ことシド・カトレットをジャズ史上最高のドラマーに推す方も少なくない。“ビッグ・シド”と呼ばれたのは堂々たる体格だったこともあるが、それ以上に、ニューオリンズ・スタイルからビ・バップまで、コンボからビッグ・バンドまで、あらゆる演奏に適応できる柔軟性をそなえた、ドラマーの鑑というべき大物だったからだ。クルーパのような大車輪のドラミングで圧倒するわけではないが、正確無比なビート、無駄のないフィル・イン、ツボを得た痛快なショットなど、趣味のよい玄人好みの名手だった。
インディアナ州エヴァンスヴィルで生まれる。幼い頃にスティックさばきを学んだ。28年にシカゴでプロ入りする。10月のアルバート・ウィン(トロンボーン)との初録音ではズッティをモダンにしたような印象を覚える。30年にニューヨークに進出、ベニー・カーター楽団をはじめ一流バンドを渡り歩き、多くのセッションにも参加、引く手あまたとなった。カーター楽団時代の録音は良好とはいえないが、注目すべきはハイ・ハットのレガート打法とニューオリンズ伝来のロール打法(注)、新旧の奏法が共存していることだ。
ロール打法に、同時期にシカゴで活動していたドッズやズッティの影が見てとれる。のちにブルーノートのトラディショナル・セッションで重用されたのは、そのスピリットを体得していたからだろう。一方で、古臭いウッド・ブロックは使わない。伝統と革新、緊張と弛緩、抑制と解放の按配が絶妙で、優れたバランス感覚を物語る。初期のスタイルの全貌をつかむには、フレッチャー・ヘンダーソン楽団の録音が最適だ。クラーク、ブレイキー、マックス・ローチに見られるスタティックな面はシドをモデルにしていると思う。
注:「ダーダッ、ダーダッ」とビートを刻む。1拍目と3拍目の「ダー」がロールだ。
●ジョー・ジョーンズ(1911‐1985)
近代ドラミングの創始者
ジョー・ジョーンズは、基本ビートのキープをバス・ドラムの4つ踏みから、ハイ・ハットのレガートに置き換え、近代ドラミングを創始した。ハイ・ハットのレガート奏法はジョーンス以前にもあった。しかし、それが何小節も続けられることはない。半コーラスをもこえる間断のないビートはジョーンズが編み出したものだ。ビ・バップの勃興期にクラークによってレガートはハイ・ハットからトップ・シンバルに置き換えられるが、ジョーンズが編み出した“連続するビート”はジャズ・ドラミングの基本であり続けている。
シカゴで生まれアラバマで育つ。13歳で学校を中退、旅の一座でタップ・ダンサー兼ドラマーとして活動し、やがてドラムスに専念する。20年代末にウォルター・ペイジ楽団に参加するが録音はない。初録音は31年4月、ヴィクトリア・スパイヴィ(ブルース歌手)のセッションだ。シンバルくらいしか聴こえずもどかしいが、ニューオリンズ派のドラマーに通じるテイストは感じとれる。34年にカウント・ベイシー楽団に参加、48年まで“オール・アメリカン・リズム・セクション”と称えられたリズム隊にあって名声を博した。
バップ・ドラミングを示唆
ジョーンズが革新的な奏法を編み出していく過程をとらえた録音はない。次いでジョーンズの演奏が聴けるのは36年10月、ベイシー・コンボの録音(レスター・ヤングの初録音でもある)だ。ハイ・ハットの不断のレガート、経済的なショット、適材適所のフィル・イン、アクセント程度のバス・ドラムといったスタイルが完成している。これに続くベイシー楽団の名演も聴き逃せないが、より貴重なのは当時の放送録音だ。ジョーンズのドラミングの全貌がよくとらえられ、ジャズ・ドラミングの発展を知るうえでも欠かせない。
ジョーンズが登場したのはビッグ・バンドの全盛期、被影響者にビッグ・バンド出身者が多いのは当然だ。リッチ、ベルソン、ルイスは大なり小なりジョーンズの影響も受けている。ベイシー楽団の第2黄金期を支えたソニー・ペインも忘れてはならない。初期のローチにもジョーンズの影はうかがえる。最大の後継者は、ジョーンズにヒントを得て、モダン・ジャズの原点となったビ・バップのビートを確立したクラークということになる。
●参考音源(抜粋)
[The Prehistory of the Jazz Drums]
Original Dixieland Jazz Band Vol.2: (17.1-23.4 EPM)
New Orleans Rhythm Kings and Jelly Roll Morton (22.8-23.7 Milestone)
Baby Dodds: The Complete Hot Five and Hot Seven Recordings (27.4 & 5 SME)
Zutty Singleton: as above (28.6-12 SME)
Gene Krupa: Eddie Condon 1927-1938 (27.12-28.7 Classics)
Dave Tough: Tommy Dorsey (36.4-39.5 Bluebird)
[Chick Webb]
Spinnin' the Webb/Chick Webb (29.6-39.2 GRP)
Rhythm Man/Chick Webb (31.3-34.11 HEP)
The Early Years-Part 1/Ella Fitzgerald (35.6-38.10 GRP)
[Sid Catlett]
Punch Miller & Albert Wynn (28.10 RST)
Benny Carter 1929-1933 (32.6-33.5 Classics)
Sugar Foot Stomp/Fletcher Henderson (36.4-8 BMG)
[Jo Jones]
Lester Young Memorial Album (36.11-40.11 SME)
The Complete Decca Recordings/Count Basie (37.1-39.2 GRP)
The Golden Years Vol.1/Count Basie (37.6 & 11 EPM)































