


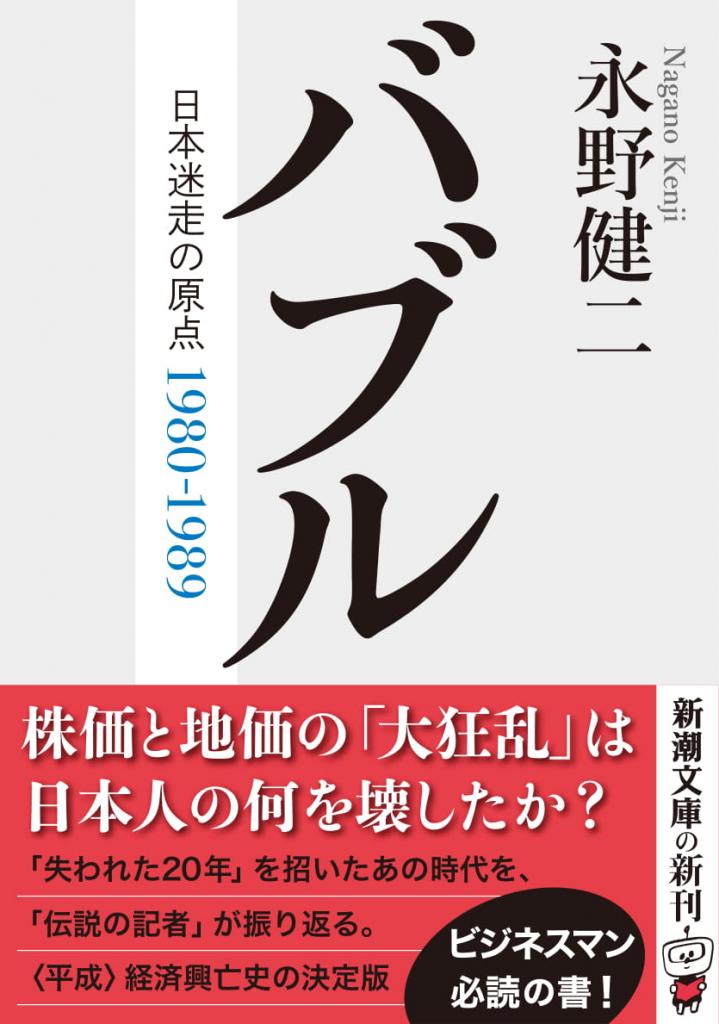
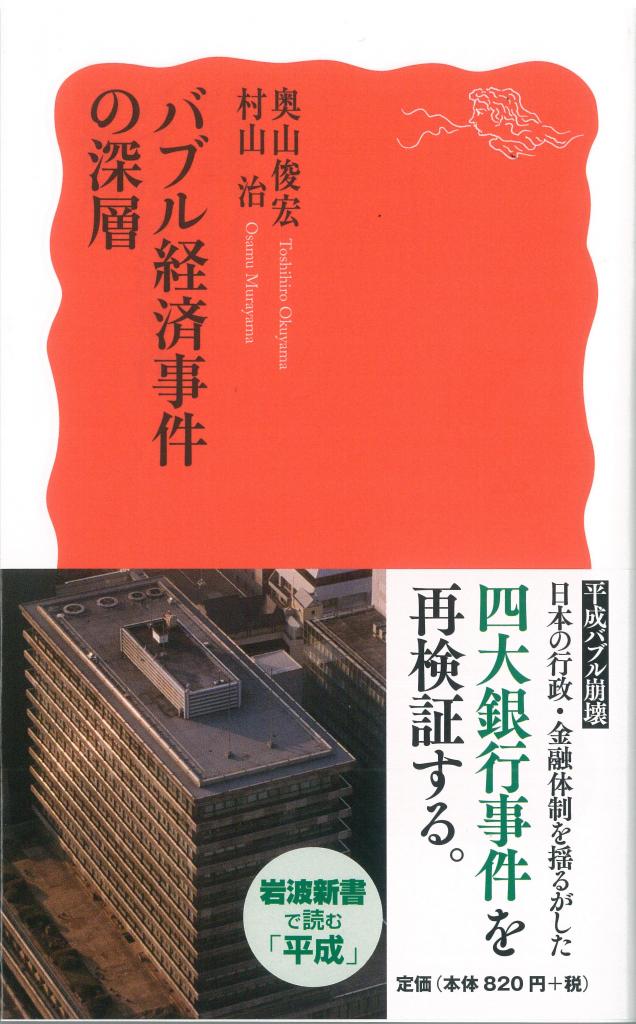
令和の時代に入ったとたん、米中の対立が深刻になり、景気の先行きが怪しくなってきた。経済に限らず、孤独死や認知症患者の急増など、これからの数十年には様々なリスクが想定される。厳しい将来に備えるため必要なのは、過去の失敗に学ぶこと。そのためにいまやるべきは、日本を長期低迷させたバブル崩壊の検証だ。今回は、問題に深く切り込んだ3人の特ダネ記者に、失敗の本質について語ってもらった。
平成はバブル経済真っ盛りの1989年に始まった。大きく膨らんだ泡がはじけると、社会は混乱し経済は長く低迷。いまや「失われた20年」を超え、「失われた30年」とも言われる。
バブル崩壊の影響がここまで深刻になった理由はいろいろある。政治や行政、企業のリーダーは保身に走り、不良債権処理などの問題を先送り。多くの国民は金もうけに熱狂し、痛みを伴う改革に背を向けた。銀行が破綻(はたん)し経営者らの刑事責任が問われたが、捜査機関の対応は後手に回った。
アベノミクスで株価が上昇し、経済はいったん回復したように見えるが、政治や行政、企業の“先送り体質”はいまも変わっていない。
こうした失敗の本質を探る本が、ここに来て注目されている。
元日本経済新聞記者の永野健二さん(69)の「バブル―日本迷走の原点―」(新潮文庫)は、2016年11月に出版された書籍が今年4月に文庫になった。霞が関や銀行がチェック機能を失って問題をごまかし続け、「第二の敗戦」とも言うべき痛手を被ったことを、当時のキーマンへの取材をもとに描く。バブルを完全に防ぐことはできないが、悪影響をできるだけ小さくすることはできると指摘。時代に真摯(しんし)に向き合う「謙虚さ」が、私たちに求められているという。
4月の新刊「バブル経済事件の深層」(岩波新書)は、朝日新聞の社会部記者として検察などを取材してきた奥山俊宏さん(53)、村山治さん(68)の共著だ。銀行を巡る事件を追った記者の目を通じて、“バブルの真犯人”を浮かび上がらせている。大蔵省を頂点とする護送船団型のシステムが機能しなくなったのに、旧来の慣行にとらわれ、新しいシステムのための環境整備を怠った。崩壊を始めたバブルの現実に、当事者たちは目を背けてしまった・・・。
今回、3人の著者にそろって話を聞いた。共通していたのは、「きちんと検証しないと同じ失敗を繰り返す」という危機感だ。
永野さんは証券業界を担当し数々の特ダネをものにした「伝説の記者」。バブルの背景には、銀行の護送船団方式など日本の経済システムが、グローバル化の時代にそぐわなくなったことがあるという。
永野さんはそのシステムを「渋沢資本主義」と呼ぶ。日本の資本主義の父とされ、新しい1万円札の肖像にもなる渋沢栄一のことだ。
「文庫になった本では、全体像でバブルの時代を語ることに主眼を置いています。高度成長を支えてきた政官財の仕組みは、世界的な自由化の流れを受けて、1980年代には変わらなければいけませんでした。でも、リーダーたちは構造改革に向き合わなかった。銀行は土地を担保にお金をどんどん貸し、大蔵省もそれを認め、官民一体でバブルを大きくしてしまった。バブルに踊っている人も悪いけれど、そこにお金を貸している銀行の責任はどうなるのか。経済の最前線で取材していて、そういう問題意識が当時からありました」



































