
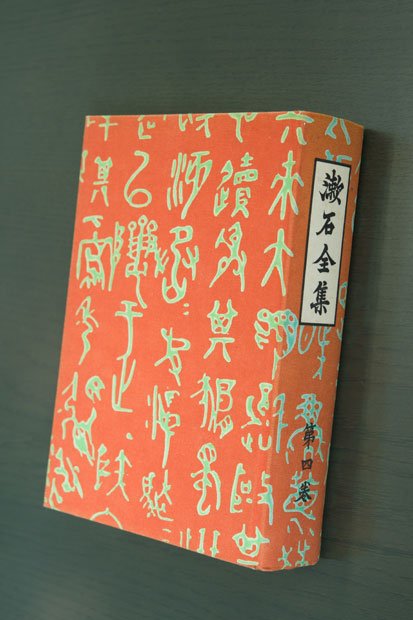
今年は夏目漱石が亡くなって100年。『坊っちゃん』『吾輩は猫である』と、今も色あせない作品の数々は各方面にファンが多い。漱石好きを自認する姜尚中さんに、漱石の魅力を語ってもらった。
* * *
高1の終わりくらいに『こころ』から読み始め、いわゆる中期3部作を読みました。『門』を読んだときはぜんぜんわからなくておもしろくなかった。年を重ねて夫婦の機微がわかるようになって、やっと理解できるようになりました。
漱石は「今」読んだら新しい発見があるはずで、私にとってはそれが『門』でした。宗助と御米という二人が、崖の下で隠花植物みたいに古いいろいろなものを背負って生きています。よく読むと最初と最後が同じシーンです。最初に縁側で日なたぼっこをしている二人の間に会話があり、最後も二人が縁側で日なたぼっこをしながら変哲のない会話をします。
若いときは、何だこんなのくだらないと思ったんですが、夫婦というものを経験すると、男と女の行きつく先の会話はこういうものじゃないかと思うようになったんです。何十年連れ添ってきても夫婦は他人だと思います。でもその人がいないと生きていけない。『門』は高校時代に読むのは早かったと思います。
漱石文学には「ダ・ヴィンチ・コード」ならぬ「漱石コード」が埋め込まれているのではないですか。若いときに読んでもわからない、わかるには年をとらないといけない。
今となっては一番好きなのは『門』になりましたが、『こころ』も大好きです。『こころ』は「先生と私」「両親と私」、そして「先生と遺書」の3部構成です。先生と「私」という年齢の離れた二人が鎌倉で出会って師弟関係が結ばれる。お互いが相手を選んだことになります。先生は自分の秘密を誰かに話したいと思っていて「私」を選びました。
この小説は人間が人間を信じる力が試されているのではないかと思います。先生は「私」を信じて打ち明けるわけです。だから何度も「あなたは真面目ですか」という言葉が出てきます。先生の「一度でいいから人を信じたい」という気持ちの表れなんですね。「私」が先生との約束をたがえるはずはない、と僕は解釈しています。先生は「私」という人を見つけて初めて、自分は死んでもいいと思ったんでしょう。
あの時代、新聞で漱石を読めて理解できた人たちは都市型のインテリで中流の人たちしかいませんでした。みんなが読めて理解するのに100年かかったことになります。やっと漱石のテーマを大衆化できる状況になりました。今読んでも決して古くなっていないんです。それは彼の2年間のロンドン体験が大きかったのではないでしょうか。
大都会ロンドンで彼が見たものが、日本を育成したのでしょう。文明は人間が疎外されるものと考えたことで、漱石は近代というつきものが落ちた人ではないでしょうか。ひとことでいうなら「自己解体」の危機です。異質の文明を受け入れるかノーなのか。自己解体を迫られると行動様式は二つあります。ひとつは西洋にかぶれること、そのアンチテーゼが国粋です。漱石はどちらにも向かなかった強靱な意志の持ち主です。近代というつきものが落ちてヨーロッパコンプレックスから解き放たれていったのではないかと思います。
漱石は里子に出されました。生い立ちを念頭に読むとよく出てくる言葉が「因果」なんです。引き受けざるを得ない哀れさみたいなものを彼は持っていた。それは『草枕』のラストでの那美さんにも表されているんです。漱石は孤独からくる、人の哀れさを見つめていたんですね。
※週刊朝日 2016年12月30日号





































