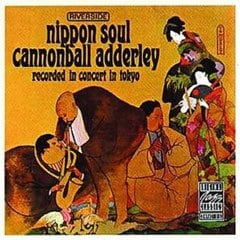
Nippon Soul / Cannonball Adderley Sextet (Riverside)
Recorded At Sankei Hall, Tokyo, May 21, 1963
1963年、来日ジャズ・グループは前年の6グループから20グループに激増する。61年正月のジャズ・メッセンジャーズ以来、62年正月にはホレス・シルヴァー・クインテット、63年正月にはジャズ・メッセンジャーズが再来日、7月にはキャノンボール・アダレイ・セクステットが初来日した。第一級のモダン・ジャズ・グループの来日が進んだ背景には我が国の聴衆の真摯で熱心な姿勢が伝わっていたということもあったようだ。このラインアップにはファンキー熱いまだ冷めずといった招聘側の読みも窺えるが、当のグループはアーシーなハードバップとでもいうべきファンキーを脱して新たな方向を目指していた。ジャズ・メッセンジャーズはフロントを3管に拡充してモードに転じていたし、キャノンボールもグループを3管セクステットに再編、アーシーなハードバップ一辺倒ではなくてモードへの試みも示すなど進路を模索していた。初来日時は過渡期にあったと言えよう。
セクステットの顔ぶれは、ナット・アダレイ(コルネット)、キャノンボール・アダレイ(アルト・サックス)、ユセフ・ラティーフ(テナー・サックス、フルート、オーボエ)、ジョー・ザヴィヌル(ピアノ)、サム・ジョーンズ(ベース)、ルイ・ヘイズ(ドラムス)というもので、既に1年半以上も行動を共にしていてグループのまとまりは磐石だった。来日コンサートの記録は東京での13曲が残されている。9日の厚生年金会館ホールでの4曲、14日のサンケイ・ホールでの4曲、15日の同所での5曲で、これらは放送音源や私的録音などの発掘ものではなくて日本フィリップスの協力を得て録られた公式録音だ。推薦盤には15日の4曲、14日の2曲、9日の1曲(追加)が収録されている。これまでとりあげた諸作のように、ある日のステージをあったがままに楽しむことはできないが、プロデューサー、オリン・キープニュースの厳しい選択眼が知れる傑作ライヴになった。
キャノンボール作《ニッポン・ソウル》に和テイストはない。お愛想でネーミングしただけだ。ファンキーなミディアム・ブルースでウォーム・アップの趣き。グルーヴィーなキャノンボールとファンキーなザヴィヌルが互角、下世話と幽玄が交錯するラティーフと直球勝負のナットが次ぐ。スタンダード《イージー・トゥ・ラヴ》ではキャノンボールがブッチギリの激走を見せて圧巻だ。ナットとラティーフによるバック・リフも格好いい。ラティーフ作《ザ・ウィーヴァー》は新主流派の香りすら漂う清新な楽想で、独り異様なムードを醸し出すラティーフに魅かれた。ファンキーなタンゴ・ブルースと言うほかないナット作《テンゴ・タンゴ》ではキャノンボールが短距離を独走する。デューク・エリントンの《カム・サンデイ》ではザヴィヌルとジョーンズのデュオがフィーチャーされた。実に感動的な聴き物だ。ザヴィヌルが終盤のホーン・アンサンブルで見せたデューク風の精妙な編曲も素晴らしい。ラティーフが親友ジョン・コルトレーンに捧げた《ブラザー・ジョン》はアフロ・モーダルな美曲、ラティーフがオーボエでコルトレーンのソプラノ・サックスのグルーヴを体現すれば、ナットが来日公演で最高の出来を示す。CD追加曲はグループのヒット曲《ワーク・ソング》だ。輝かしいファンキー大将のキャノンボール、ニートな突撃ラッパのナット、どこか怪しげなラティーフと、三者三様の面白さがある。
このときに録音された残る6曲は『ディジーズ・ビジネス』(マイルストーン)で聴ける。出来はわずかに落ちるが、ほぼ快演級が並ぶ。キャノンボール・ファンなら見逃せまい。キャノンボールのグループは66年8月にも来日、そのときは“真っ黒”に変貌していた。キャノンボールといいシルヴァーといい、ファンキーの寵児や商人と呼ばれた時代よりもあとのほうが格段に黒いのだ。再来日時のライヴ盤もいずれとりあげようと思っている。
【収録曲一覧】
1. Nippon Soul (Nihon No Soul)
2. Easy To Love
3. The Weaver
4. Tengo Tango
5. Come Sunday
6. Brother John
7. Work Song [CD Bonus Track]
Nat Adderley (cor), Julian “Cannonball” Adderley (as), Yusef Lateef (ts, fl, oboe), Joe Zawinul (p), Sam Jones (b), Louis Hayes (ds)

































