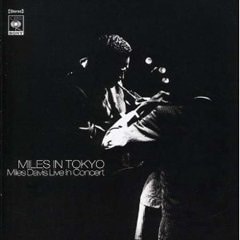
円高ということもあって、こぞって外タレが来日したバブル全盛の頃、友人がロン・カーターを観に行くといって、どこからか『マイルス・イン・トーキョー』のレコードを借りてきた。
まったくジャズには疎い彼だったが、景気のよかった時代のこと、「大物が来たら、とりあえず観ておけ」というんで、『マイルス・イン・トーキョー』で“予習”するのだという。
'90年代はじめのロン・カーターを観に行くのに、'60年代にサイドマンで参加した『マイルス・イン・トーキョー』を聴いて、何か参考になるのかしらん?と思いながらも、“予習”に意欲的な彼には黙っていた。
ロックやポピュラー音楽のミュージシャンが来日するときには、とりあえず最新アルバムと代表作を“予習”しておいて、本番で演奏されると、昨日初めて聞いた曲でも、もう何十年も前から知っていたかのように、「イエーイ!」なんて叫んで盛り上がるのが一般的なライブの楽しみ方だったが、ジャズの場合、毎回レコードと同じような型にはまった演奏をするわけではないので、あまり“予習”の効き目がない。
わたしなどむしろ、レコードと同じアレンジで演られたりするとがっかりする。
まったく予備知識なしに聴いて、一発で感動を与えるのが音楽の本来の姿であると思うが、なかなかジャズのレコードを一回聴いて、ハイわかりました!とならないのも事実である。何回も何回も繰り返し聴いて、ようやくはたと膝を叩くこともあれば、何回聴いてもよさがわからぬこともある。
ところが、ジャズの生演奏を聴けば、それまでジャズにまったく興味のなかった人が、パッと理解できたりする。いきなり楽しめることがある。音楽とリスナーのあいだに、オーディオという余計なものが介在しないからである。
ジャズを難解なものにしている真犯人はオーディオ装置であって、上手な人の生演奏を聴かせれば、なあんだ、こういうことかとすぐに合点がいく。
はやい話が、いい音で聴けばジャズがわかりやすく、悪い音だとわかりにくい、というだけのこと。聴く人の頭の良し悪しなど関係ないのだ。
混乱しやすいのは、オーディオ装置が毎回同じ音で鳴らない、つまり、いい音で鳴ったり鳴らなかったりするために、音楽がわかりやすかったり、わかりにくかったりすることである。
同じ曲でも、一回目にかけたとき、オーディオ装置がいい音で鳴るか、それとも100回目にようやくいい音で鳴って理解するか、それはもう人それぞれであるから、他人様に「必ず100回聴かないとわからない」とかいっていじめてはいけません。
そういえば、近頃、別のジャズ好きの友人が、高価なオリジナル盤LPを買っては聴き、すぐまたオークションで売るという、ジャズファンには珍しい聴き方を編み出した。
大量のレコードを置いておくスペースも、ストックしておく資金もないから、音のいいオリジナル盤をちょっと聴いて、即オークションに出す。うまくいけば利益が出るのだという。
これなんかもう、極上のオリジナル盤を手元に置いて繰り返し聴きたいという執着を断った、まさに一撃必殺の聴き方である。また聴きたくなったら、彼はおそらくまた同じオリジナル盤を買うのだろう。まったく恐れ入る。
【収録曲一覧】
1. Introduction By Teruo Isono
2. If I Were A Bell
3. My Funny Valentine
4. So What
5. Walkin'
6. All Of You
7. Go-Go (Theme And Announcement)

































