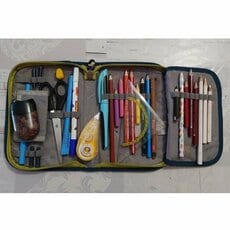早生まれのお子さんの学業や受験に関心を持たれている方も多いと思います。「実は私も、息子が早生まれであることを強く意識したのが、中学受験のときでした」と語るのは脳医学者の瀧靖之さん。多くの親御さんが受験のときに抱くであろうモヤモヤについて、瀧さんの著書『本当はすごい早生まれ』(飛鳥新社)から紹介します。
【表】学力の高い家庭がやっている生活習慣はこちら中学受験での体験が脳に与える影響
早生まれだからといって脳の能力が劣っているわけでも、本来の学力が低いわけでもありません。ただ中学受験の段階では、発達の差が残っているか、もしくは早い段階で遅生まれの子との間に成績に差がつくことで、自己肯定感を下げている可能性があるかもしれません。
私は、自己肯定感は早生まれ族の能力を伸ばすキーになると考えています。
脳は「努力」と「褒める」で、物理的に良い方向へ変化していきます。ですから間違っても、中学受験を「叱る機会」にして、自己肯定感を下げてはいけないと思います。不利な状態で臨まなければならない中学受験では特に、成績という「結果」に着目するのではなく、勉強をするという「努力」に着目した方が良いと思うのです。そして「努力」に注目した方が、自己肯定感が高まります。自己肯定感が高まれば、自ずと成績は上がっていきます。
ですから、自己肯定感をわざわざ下げるような物言いはやめた方が良いのです。「早生まれだから成績が悪い」といった、子どもに呪いをかけるような発言は、どんなにイライラしても我慢した方がいいでしょう。
では「早生まれだから仕方ない」といった声かけはどうでしょう。小学校の先生に話を聞いたところ、こういった声かけには、プラス面とマイナス面の両方があるといいます。
プラス面は、子どもを追い込まずにすむことです。頑張りすぎて心が折れる危険を、この言葉で回避することができます。しかし、マイナス面もあります。もっと頑張れるのに「早生まれだから仕方ない」と、自ら努力することを諦めてしまうことにつながるというのです。
次のページへ中学受験は「脳トレ」