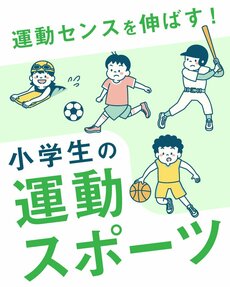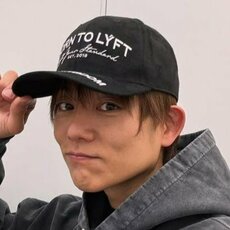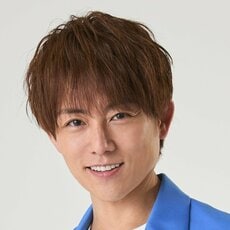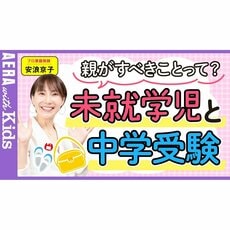子どもたちの直観は当たる
矢萩:そうですね。その学校の持っている「場の力」みたいなのものってすごくありますからそれを体感するのは大事ですね。そこが相性に合いそうか、理想的かどうか、というのはしっかり見たほうがいいです。

安浪:1年生だとまだいないかもしれませんが、モンスターペアレントが出てきたりすることもあるじゃないですか。その一団があっちの中学行く、となったらと、あの人たちが行く中学は避けよう、とかもあるかもしれない。
矢萩:もちろん、進学先の候補になる中学についてもしっかり調べたほうがいいです。4年生ぐらいになったら息子さんと一緒に行って相性を確かめることも大事です。うちの塾に通っている生徒が第一志望にしていた学校説明会に行って、在校生から直接話を聞く機会があったらしいんですが、帰ってきたら第一志望変えたいですって言い出して。何で?って聞いたら、在校生の人が偏差値の話ばっかりしてきたというんですね。そういう指標の話をするのが好きならその環境に行ったらいいし、そういう話に違和感があるようなら、その学校に行ってもあまりハッピーにならないかもしれない。その生徒の感想だけで決めていいの?と思うかもしれませんが、意外とそういう直観って当たっていたりするものです。
安浪:学校はナマモノなので、それこそ校長が変われば、学校説明会に行っても、1年前に感じたのと今年感じるものが違うという可能性も珍しくないと思います。あと、今は情報過多なので家庭の価値観も刻々と変わるので、同じ説明を受けても、以前抱いた感想と違う印象を持つこともあると思います。
矢萩:私学か地元の公立か、偏差値が高いか、低いかに関わらず、学校によって集まりがちな生徒というのはいます。学校のハード面はもちろんですが、そのようなソフト面、どんな生徒たち、どんな保護者が集まりやすいのかを分析することは、すごく大事だと思います。特にその地元の中学校が嫌だ、なんかここじゃないと思っているのだったら環境を大事にしたい、ということだと思うので、選ぶ先の環境も同じ目線で見たほうがいいと思います。
(構成/教育エディター・江口祐子)