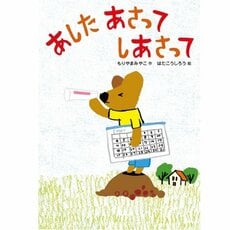都市部を中心に人気が続く中学受験。首都圏の受験率は2024年、過去最高を更新しました。中学入試や中高一貫校の最新トピックを紹介するAERA with Kids+の連載。今回は、社会の変化に応じて変わりゆく私立中高一貫校と学校選びの視点について、中学受験情報誌「進学レーダー」前編集長の井上修さん(現・日能研入試情報室室長)が解説します。
【図】こんなに変化!中高一貫校6年間での学びの「昔」と「今」(全3枚)社会の変化で、中高で「学びたい学問」を考えることが重要に
現在、会社や研究機関の組織は大きく変化しています。端的には「上意下達型組織」から「グループ・プロジェクト型組織」への移行です。社会と世界は激動の時代に突入していますが、このような時代に硬直した上意下達型の組織では変化に迅速かつ効果的に対応することはできません。そのため、組織がさまざまな意見を常時吸い上げ、柔軟に取り組むことが常に求められるので、グループ・プロジェクト型に移行しているのです。この組織では、「非認知スキル」がとても大事になります。この「非認知スキル」は読み書きなど学力で測れない力のことで、協調性、やり遂げる力、自己肯定感、自己管理能力などが含まれます。
このグループ・プロジェクト型組織でもう一つ大事なのは「自分の得意は何か」をはっきりさせることでしょう。つまり、大学で何を学んできて、その学びを通して、会社でどう貢献できるかということなのです。実際、社会に出た後に、職場やビジネスの現場で、自分の出身大学の話を頻繁にするでしょうか。もしくはその話は重要でしょうか。おそらく、そんな状況はあまりなく、話題の一つ程度でしょう。むしろ、自分の出身大学をひけらかす人は敬遠されるのではないでしょうか。自分の専門を生かし、やりたい分野で働きたいもの。学びたい学問を学び、それを生かせる職場で働ければ、それこそ自己実現でしょう。
ゆえに、大事なのは中高の段階で、何を学びたいのかをしっかりと考えて、学びたい学問領域、そして学部・学科を探していくことです。その際、難関大学に入ることができれば、特に保護者の喜びも大きいでしょうが、近年は大学の評価が変動し、今後さらに大きく変動していきます。
次のページへ理系人気の背景に「高大連携」