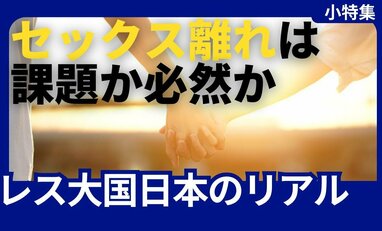服の素材として幅広く使われてきた綿の栽培には広大な農地が必要だ。水や農薬も必要で土地へのダメージが大きく、供給不足が懸念されている。一方、石油が原料のポリエステル素材は、速乾性や通気性、耐久性に富むなど、天然繊維にはない特長を備えている。このため2000年以降は綿を抜き、繊維生産量の約6割(5200万トン)を占めるようになった。
「そのポリエステルは弊社の工場が稼働し、事業が継続している限り、何百年でも再生できます。着なくなった服は回収して再生する『服から服へ』という文化を世界中の人々の意識に根付かせたいと考えています」(中村さん)
同社のポリエステル再生技術は、何度でも繰り返し再生が可能だ。200グラムの再生ポリエステルで1枚のTシャツを作ることができるという。
■あらゆるモノを循環
「厳密には、再生処理でポリエステル繊維の質量が96%に減ります。100グラムであれば96グラム。TシャツのLサイズがMサイズになる感覚です」
同社は「あらゆるモノを循環させる」というビジョンの実現に向け、服の素材を問わず回収している。古着は北九州市の自社工場に運ばれ、素材や混合比率によって分類。自社工場で再生処理しているのはポリエステルのみだが、それ以外の素材は協力会社に移送し、ウールは再生ウール、綿は自動車内装材、ファスナーなどの金属類はコークス炉でコークスの代替となる還元剤としてそれぞれ活用されている。
店頭で回収した服の中には、クリーニング袋に入ったものや購入時の値札がついたままの服もあり、古着としてリユース(再使用)に回すケースも少なくないという。
19年に国連貿易開発会議(UNCTAD)が発表した資料によると、世界のファッション業界は、年間930億立方メートル(約500万人分の年間飲料水と同量)の水を利用し、約50万トンのマイクロファイバー(石油300万バレル相当)を海洋に投棄。航空と海運業界を足したものよりも多い12億トンのCO2を排出しており、石油産業に次ぐ、2番目の「環境汚染産業」とされている。
こうした中、SDGsの浸透も相まって国内アパレルも環境負荷への意識を強めている。
同社が店舗での古着回収事業として09年に立ち上げた「BRING(ブリング)」は当初、無印良品など6ブランドでスタートしたが、今ではGUやパタゴニア、高島屋など約120社が参加。月平均3500拠点の様々なブランドの店頭で年間500~600トンの古着を回収している。