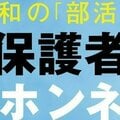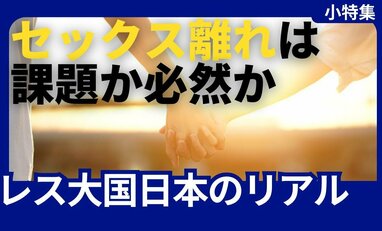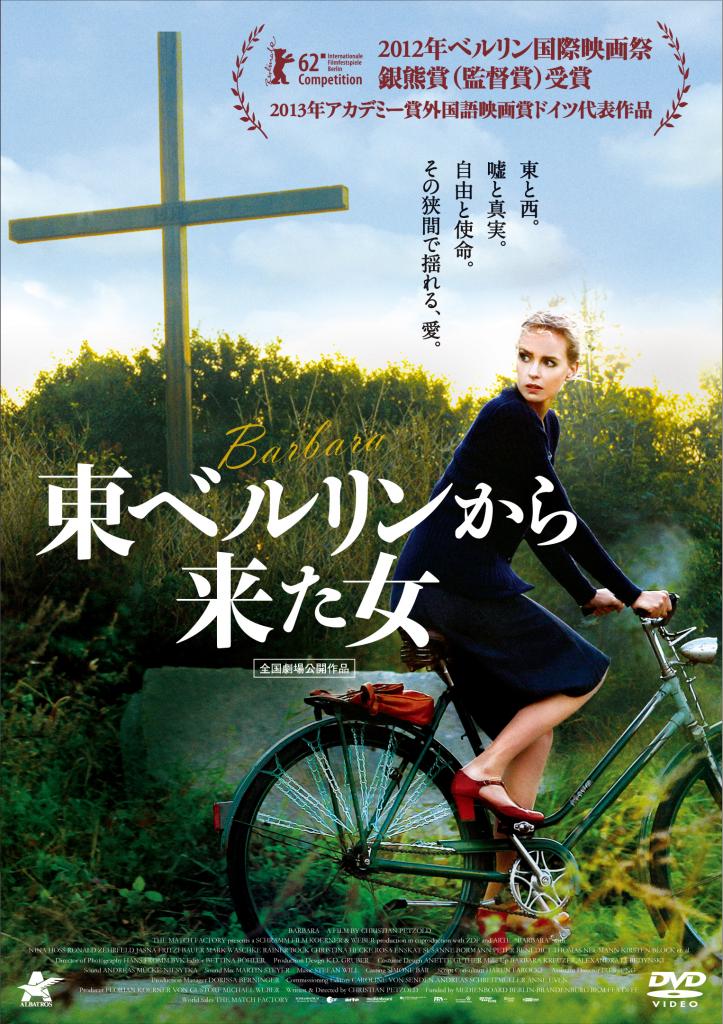
AERAで連載中の「いま観るシネマ」では、毎週、数多く公開されている映画の中から、いま観ておくべき作品の舞台裏を監督や演者に直接インタビューして紹介。「もう1本 おすすめDVD」では、あわせて観て欲しい1本をセレクトしています。
* * *
誰もいなくなった深夜の大型スーパー。フォークリフトがまるで意思を持っているかのように、しなやかに動き出す。流れるのはヨハン・シュトラウス2世の「美しき青きドナウ」。「舞台は旧東ドイツのスーパー」と聞いて無機質な空間を想像していたが、そんな思い込みは一瞬で吹き飛ぶ。幻想的で、心が洗われるようなオープニングだ。
「希望の灯り」は、短編小説を原作とする。だが冒頭のシーンはトーマス・ステューバー監督(38)が映画化にあたり意図的に加えたのだという。
「社会批判をするために映画を撮りたかったわけではないんだ。それよりもアキ・カウリスマキの作品のような浮遊感のあるタッチにしたかった。そんな姿勢を冒頭のシーンで示したいと思いました」
ベルリンの壁崩壊後のライプチヒ近郊。スーパーの在庫管理係として働き始めたクリスティアン(フランツ・ロゴフスキ)はそこで働く年上のマリオンに心惹かれる。商品棚を隔てて交わされる二人の視線、クリスマスの夜、スーパーの裏で仲間たちとビールを飲む時間。描かれるのは、とてつもなく小さな世界の何げない日常だ。
大きな事件という事件は起こらない。それでも飽きずに観続けてしまうから不思議だ。彼らに寄り添うのは、クラシックの名曲だったり、知る人ぞ知るロックの楽曲であったり。音楽は多用されるが、登場人物の感情を観客に押し付けることはない。
「昼間は、誰もが軽く聞き流せるような曲が流れている。でも夜になり客がいなくなると、そうした音楽に飽き飽きした店員たちがクラシックを聴いているかもしれない。そんなところから想起していきました」
登場人物たちはみな、多くは語らない。それでも彼らの表情や話し方からは少しの寂しさや孤独を感じる。どのように生きてきたのだろう。なぜこのスーパーにたどり着いたのだろう。ステューバー監督は俳優たちに登場人物の感情を逐一説明することはなかったが、彼らは脚本を読んだだけで、その心をつかんでくれたという。