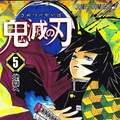前出の有力OBは「このままでは、ホンダとその下請け企業は衰退の一途。いずれまとめて外資に買収される可能性が高い。雇用など国益を考えれば大胆な打開策が必要。日産・ルノー・三菱連合に加わるべきではないか」と提言する。
これは絵空事ではない。
実際、バブル経済崩壊後に、メインバンクが同じ三菱自動車とホンダの経営統合が画策されたことがあるのだ。
最近でも「複数のホンダ系有力部品メーカーをドイツのメガサプライヤーであるコンチネンタルに丸ごと売却する構想が進んでいたが、条件が合わずに頓挫した」(ホンダ関係者)と言われている。
一方で、日産は「ゴーン事件」以来、ルノーとの関係がぎくしゃくしている。スナール・ルノー新会長が来日して、3社連合の重要性を再確認したばかりだが、日産の会長ポストを巡る攻防など、主導権争いが今後激しくなる恐れもある。
その間、共同開発や共同生産など事業面は停滞するだろう。北米事業の不振で、業績下振れもありうる。このままだと、3社の連携は一気に「弱者連合」と化す可能性が高まっている。
3社連合にホンダが加わるべきとの提言には、「非トヨタグループ」をつくるねらいも含まれている。
まず日産系、ホンダ系、三菱系の部品メーカーが開発や調達などの面で緩やかに連携する。それに加え、日産から多くの人材を受け入れているモーター大手の日本電産を巻き込む戦略だ。モーターは電動化時代に欠かせない基幹部品。対するトヨタはすでに、ブレーキ事業や電子部品事業の集約など、グループ企業の部品メーカー再編で、競争力強化を着々と進めている。
弱肉強食の動物の世界では、天敵がなくなると緊張感が途切れたり、繁殖しすぎてかえって絶滅の危機に瀕したりするという。日産、三菱、ホンダの衰えは、トヨタから緊張感を奪うことにもなるのではないか。国内が基盤の2大グループが競い合うことで、日本の自動車産業に競争力を残すことができる、との見方も捨てたものではない。
筆者は20年以上、経済記者として自動車産業をウォッチしてきた。その経験からして、ホンダの英国生産撤退や、3社連合のゆらぎは、自動車産業大再編の予兆の気がしてならない。(ジャーナリスト・井上久男)
※週刊朝日 2019年3月8日号