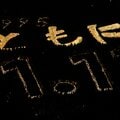南海トラフ地震について国の有識者会議が5月28日、「現在の科学的知見からは確度の高い予測(=予知)は難しい」とする最終報告書をまとめた。しかし地震学的な視点からは予知が困難だとしても、巨大地震には周期性があることがわかっている。古文書や寺社の記録、地層から過去の地震について調べる「地震考古学」の観点から見てみると、最近の地震の周期は9世紀と重なる点が多いという。
この「地震考古学」の提唱者、産業技術総合研究所の寒川旭(さんがわあきら)・客員研究員が語る。「ここ50年間の地震の発生状況は9世紀に非常に似ているのです」。
9世紀に発生した大地震を見ていくと、818年の北関東地震以後、東北地方の日本海側や関東甲信越地方で内陸型の地震が多発していることがわかる。そして869年、東日本大震災を引き起こした巨大地震とほぼ同じ震源、規模の貞観地震が発生した。
そこから9年後の878年には首都直下とも言える南関東地震が、さらにその9年後の887年に南海トラフ地震の仁和東海・南海地震が起きた。
それと比べて、最近50年間の状況はどうか。ぴったり一致はしないものの、9世紀と同様に新潟地震(64年)、日本海中部地震(83年)、など、関東甲信越、東北の日本海側、西日本で巨大地震が起きていることがわかる。
9世紀のとおりになるとすれば、貞観地震に匹敵する東日本大震災の9年後、つまりいまから7年後の2020年に首都直下地震が、2029年に南海トラフ地震が起こる?
「首都直下地震は東日本大震災に誘発されて起こると考えられ、今後10~15年間は関東地方で大地震が起きてもおかしくはない」(建築研究所の都司〈つじ〉嘉宣・特別客員研究員)
※週刊朝日 2013年6月14日号