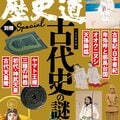これらは謀反人光秀というよりは、光秀の人間性に着目した芝居であり、光秀を「悲劇の人」と捉えている。歌舞伎の世界は、元来「忠臣蔵」「曾我物語」「平家物語」など悲劇を扱う趣向になっており、民衆はこうした悲劇を好んだことから「光秀の悲劇」も生まれた。
光秀の悲劇とは、敵役の信長(小姓・森蘭丸)に徹底的にいじめ抜かれ、最後に堪忍袋の緒が切れて本能寺の変に至るという描き方から来る。民衆には、光秀の我慢・忍耐・耐える力が好まれた。そして信長と蘭丸を討つ場面では、興奮し、涙を流して光秀を声援したというのである。 因みに歌舞伎の世界は本名を使うことを禁じられていて、信長は「小田春長」秀吉は「真柴久吉」光秀は「武智光秀」という役名であった。そして信長は、秀吉・光秀の単に主君で、しかも敵役といった立場で演じられた。
このように江戸時代は、浄瑠璃・歌舞伎・絵草紙ばかりか俳句・川柳・狂歌でも光秀は人気の対象になっていた。江戸の民衆は「時は今」「三日(天下)」「桔梗」「(明智)藪」という言葉は全て光秀に関連する事柄と知っていた。
俳人・芭蕉にも良妻賢母といわれた光秀の妻を詠んだ俳句がある。貧しい弟子の妻の心尽くしに感動した芭蕉が詠んだ句だが、光秀の妻が自らの髪や着物を売って光秀主催の宴に心を尽くしたという逸話を例に引いている。「月さびよ明智が妻の咄せむ 芭蕉」という句である。「光秀の江戸時代」は、こうして民衆人気の中に溶け込んでいたのであった。
こちらの記事もおすすめ 【前編】惨敗、敗走、死の刹那…秀吉と戦った明智光秀の脳裏に「足利尊氏の成功」があったのか