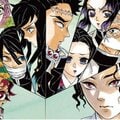子どもへの「10万円給付」と3回目のワクチン接種時期で、政府の方針は二転三転。その度に振り回される地方自治体のトップはどう思っているのか。高島宗一郎・福岡市長に、政府の対応について聞いた。AERA 2022年1月3日-1月10日合併号から。
【データ】ファイザー製ワクチン2回接種者の中和抗体値の変化はこちら
* * *
市町村のような基礎自治体は住民生活に直結する現場業務を担っています。だからこそ、ありとあらゆるトラブルの種が容易に想像できます。例えば、クーポン配布は最短で2022年3月頃という話がありました。自治体は「3月」という数字を聞くと震え上がるんですよ。福岡市の場合、1年間に約7万人が市外へ転出、約8万人が市外から転入し、特に年度の変わり目に集中します。つまり、多くの方が転出先の自治体で使えないクーポンを受け取ることになってしまうのです。また、自治体の規模によって、クーポンが使える店舗が限定されてしまうケースもあるでしょう。
10万円給付を現金とクーポンに分けると、事務経費が967億円膨らむことが取り沙汰されました。
行政からの給付は、民法の「贈与」にあたり、当事者間の同意が必要となります。そのため、福岡市では今回、現金5万円の給付通知を、対象者約11万人に郵送しました。その後、国の方針転換で10万円一括支給が可能となりましたが、本来なら、追加の5万円分の通知を再度郵送しなければなりませんでした。今回は特例で、最初の5万円の通知をもって、10万円の給付への同意とみなせるようになったのですが、仮にもう一度通知を郵送した場合、福岡市だけでも数千万円の追加費用が発生します。例えば、受給の可否確認をスマートフォンで行えるようにすれば、こういったコストが削減できます。
さらに、特定の対象者に給付する際に必要なのは「データの連携」です。例えば、給付金を受け取る口座を国民に登録してもらい、マイナンバーをキーに、課税情報などと連携できれば、必要な対象に必要な支援を迅速に届けることも可能になります。
今回の混乱から日本にとって良いものを得られるよう、マイナンバー法の整備も含め、国会議員や政府には本質的な議論を期待したいですし、国民もデジタルのメリットを考えるきっかけにしてほしいと思います。