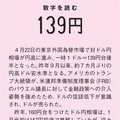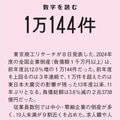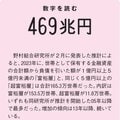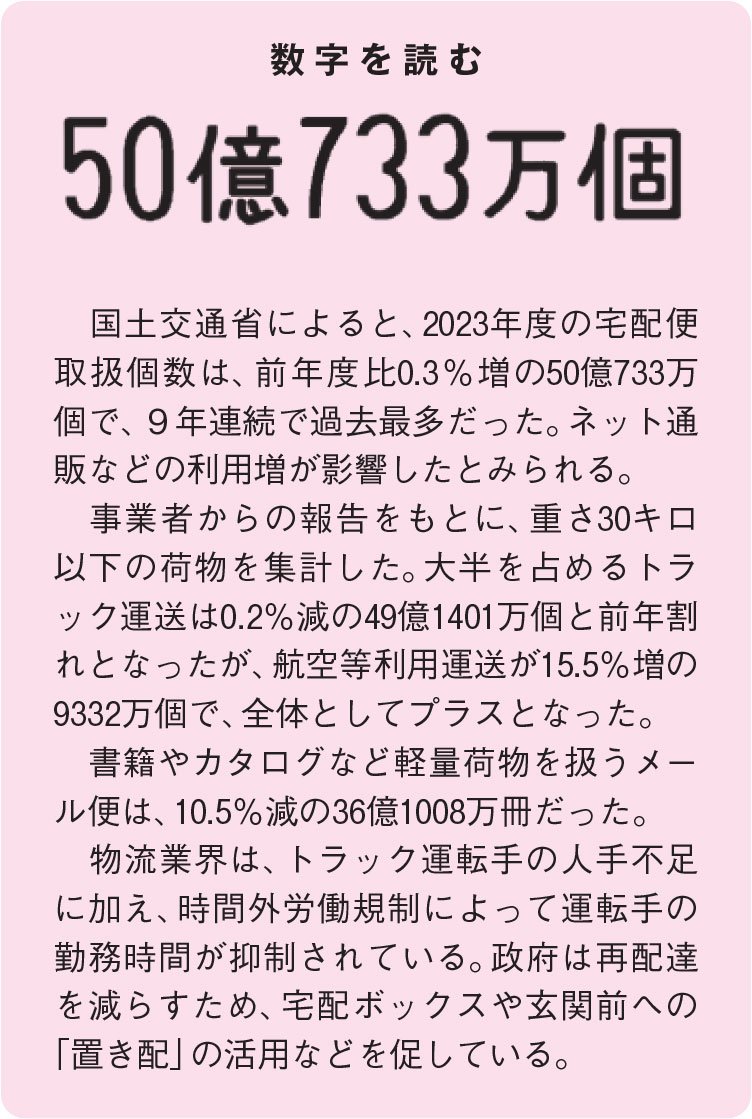
物価高や円安、金利など、刻々と変わる私たちの経済環境。この連載では、お金に縛られすぎず、日々の暮らしの“味方”になれるような、経済の新たな“見方”を示します。 AERA 2025年5月26日号より。
* * *
学校から帰ると、「西瓜」と書かれた大きな箱が玄関に届いていた。スイカの大玉が2個も入っていそうなサイズだ。みずみずしい甘さを想像し、急いで梱包を解こうとしていると、母親から「うちのじゃないよ」と咎められた。見ると確かに隣の家の宛名が書かれていた。
昭和の終わりごろは、宅配物を隣近所が預かり合うのが普通だった。不在の家があれば、配達員はためらわず近隣宅の呼び鈴を押す。頼まれた家もごく自然に荷物を受け取り、持ち主が帰宅した頃を見計らって届けてあげるような風景が日常だった。
昭和の日常は、今となっては非常識だ。隣の家の荷物を預かるなんてありえない時代になっている。再配達は増え、宅配の荷物自体も増える一方だ。2023年度、宅配便取扱個数は50億個を突破し、9年連続で過去最多を記録している。フリマアプリやネット通販が日常化し、物流量は増加の一途をたどっているのだ。
一方、日本の人口は2011年以降減り続けている。つまり荷物は増えているのに、それを運ぶ人を確保することが年々厳しくなっている。昨年からは、トラックドライバーの時間外労働を規制する法律も施行された。物流業界は配送の効率化を図るためにさまざまな努力をしている。AIによる配車管理の自動化やルート最適化を行って配送効率を高めたり、大規模な物流拠点を都市部近郊に集約し、配送ルートを最短化したりしている。
しかし、どうしても効率化が難しいのが「ラストワンマイル」、つまり荷物を個々の家まで届ける最後の部分だ。昨年、「ラストマイル」という映画が話題になったように、この問題は社会的にも注目されている。
政府も宅配ボックスや玄関前への置き配を推奨しているが、まだまだ普及していない。オートロック付きのマンションであれば、置き配することも難しい。管理人がいるマンションであれば、管理人がオートロックを解除したり、管理人が荷物を預かることを義務化したらどうだろうか。もちろん、管理側の負担を増やすことになるが、そうでもしない限り、人手不足問題の解消は難しいと思うのだ。