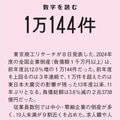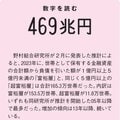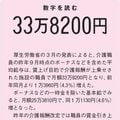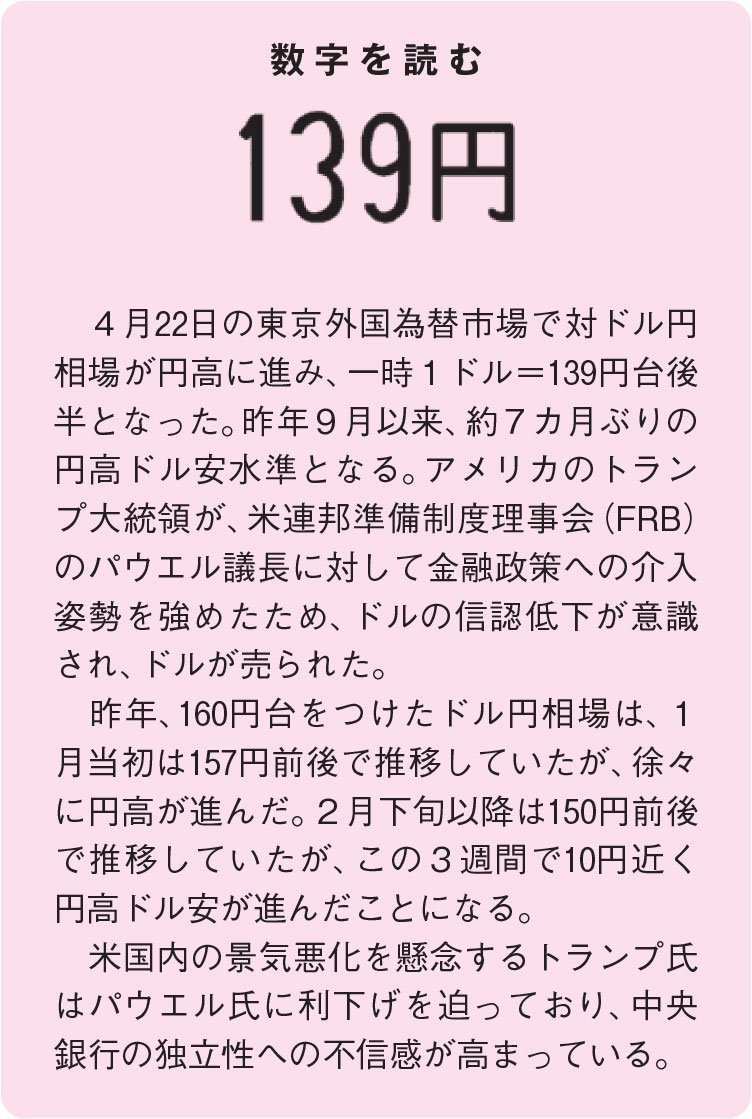
物価高や為替、金利など、刻々と変わる私たちの経済環境。この連載では、お金に縛られすぎず、日々の暮らしの“味方”になれるような、経済の新たな“見方”を示します。 AERA 2025年5月5日-5月12日合併号より。
* * *
どうして為替市場の経済ニュースは、私たち生活者の感覚とこれほどまでにずれているのだろうか。
先週、円高が140円台まで進んだが、歴史的に見ればまだまだ円安水準だ。それなのに「円高で企業収益に懸念」「円高が進むと利上げを見直す必要」など、まるで円高が経済にとっての敵であるかのようなニュースがちらほら見え始めている。これがもし1ドル=90円というような水準なら話は別だが、140円台で懸念を示すことには驚きを隠せない。
円安は長い間、日本経済にとってプラスだと信じられてきた。確かに昨年は1ドル=160円台まで円安が進んだ。しかし輸出量そのものは伸びておらず、円ベースでの売り上げは増えても、輸入コストが大きく上昇したため、多くの生活者にとってはマイナスの影響が目立った。円安が進む中で、食費や電気代を含む日常生活に必要なものの価格が軒並み高騰していることは誰もが実感しているはずだ。
先週、1ドルが140円を割り込んだタイミングで、インスタグラムで質問をしてみた。
「円安と円高、どちらがうれしいですか?」
約2500人の回答者のうち、実に72%が「円高の方がうれしい」と答え、その理由の7割以上が「物価が下がるから」としている。一方で「円安の方がうれしい」と答えた28%の人たちは、その大半が「外貨資産を多く保有しているから」と回答している。つまり、外貨投資をしていない多くの一般的な生活者にとっては、円安など百害あって一利なしなのだ。