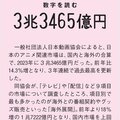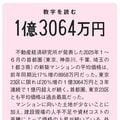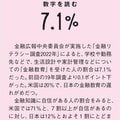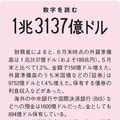さらに最近では、暗号資産やFX(外国為替証拠金取引)といった取引も盛んだ。これらは法律上「投資」として認められているが、その実態は非常にギャンブル性が高い。特にFXは最大25倍のレバレッジをかけられ(以前の500倍に比べれば改善されたが)、短期間で大きな利益や損失を生むことがある。実際、FXの年間取引額は推計で1京円を超え、オンラインカジノの年間賭け額(約1兆2423億円)の約1万倍にもなる。この巨大な取引市場の中で、刺激やスリルを求めて依存症に陥る人も少なくない。依存症患者が増えれば、その社会的コストも当然高くなる。
国内にギャンブル性の強い取引が合法的に存在している以上、オンラインカジノの違法性が浸透しないことはある意味自然だとも言える。現在の法的な曖昧さを解消するには、ギャンブルという行為を明確に定義し直す必要があるだろう。
しかしながら、一大ビジネスになってしまったパチンコやFX取引を違法にはできないだろうから、一定範囲のギャンブル性を認めた上でその収益を社会福祉や教育へ還元する仕組みを作って、社会的コストを負担してもらうのが現実的だろうか。
こうしたギャンブル的な取引が社会に浸透している背景には、経済の停滞や社会格差の拡大といった構造的な問題がある。真面目に働いても報われない、多少報われたとしても、すでに開いた格差を埋められないなら、一攫千金のロマンを追いたいと思ってしまうのも無理はない。
資産所得倍増計画も悪くないが、それ以上に大切なのは「真面目に働いている人が報われる」という当たり前でシンプルな社会なのではないだろうか。この連載でも何度か指摘しているが、いろんな場面で生活インフラが崩れつつある。生活を支える人が報われれば、社会全体がもっと明るくなるはずだ。
※AERA 2025年3月31日号