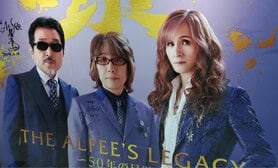3人が並んで立って同じ方向に目を向ける。たとえばそこに、オープンしたばかりの虎ノ門ヒルズがあるとする。マッカーサー道路の上に建てられた地上52階のビル。視野の端には東京タワーも見える。
この風景を眼前にし、ある人は6年後の東京オリンピックを前提にした新たなビジネスへの野望を抱くかもしれない。その隣にいた人は、またこんなもの建ててと口を歪め、衰退の一途をたどる故郷を思って溜息をつくかもしれない。もう一人は、東日本大震災時の恐ろしい体験がよみがえり、つい目をそらすかもしれない。
同じ風景と向きあっているはずなのに、これら三者はまるで違うものを見ているようだ。なぜなら、風景には見る者それぞれの気分や心象、そして過去の体験や知見が反映されるから。どうしてそう見えるか解釈を語れば、そのままひとつの物語にすらなる。
武田徹はこの『暴力的風景論』で<「風景」とは、その人が見ている世界そのものである>と指摘している。自分の気分や内面が反映され、世界観や歴史観にまで通じる風景であればこそ、<ひとたび視界に現れれば、人はそれ以外のものとして世界を見ることができなくなる>からだ。そのために人は、それ以外の風景を認めなくなり、そう見えない者たちの存在を隠蔽したり、攻撃したりするようになる。こうして、風景が暴力の源泉になっていく。
武田が提起した風景論は、ジャーナリズムの新しい可能性へのアプローチでもある。その特徴を知って風景と対峙すれば、事実に折り重なった物語や世界観や気分を読み解き、私たちがどのように世界と、時代と向きあってきたか知ることができるかもしれない。武田はこの考えにもとづいて米軍基地、富士山、マッカーサー道路など八つの風景に挑み、<その向こう側から漏れ聞こえてくる>別の風景の声に耳を澄ました。
風景をめぐる理論と実践。快著である。
※週刊朝日 2014年6月27日号