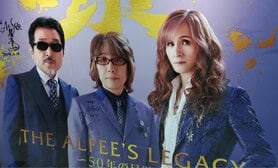「3.11を忘れない」というけれども、わざわざ「忘れない」と叫ぶこと自体が、もう忘れていることを示しているのではないか。
先日、東北在住の作家にインタビューした際にいわれた言葉だ。彼の家は半壊したままだ。
たとえば原発にしても、政府は再稼働に前のめりだ。東京電力福島第一原発の事故収束すらままならないというのに。被災地以外の人は3.11を忘れている、といわれても返す言葉がない。
門田隆将の『記者たちは海に向かった』の発行日は3月11日。帯には「時を経たからこそ語られる、地元記者たちの感動の実話」とある。そう、3年たったからこそ、振り返るべきであり、考えるべきこともあるのだ。
本書は「福島民友新聞」という地元紙の記者たちが、どのように地震に遭い、津波に遭い、放射能汚染に遭ったかを、詳細に取材したドキュメントである。
地元紙をつくる人びとに視点を置いたことで、震災の全体が見える。なぜなら彼らは被災者であると同時に取材者であり報道者であるからだ。地震・津波・放射能から避難しつつ、同時に新聞の発行を続けようとする。実際、電源が止まり、電話もつながらないなか、同紙の「紙齢」=創刊以来の連続発行番号は途切れなかった。
津波で1人の記者が死んだ。24歳の若い記者だった。地震直後に海岸を取材していて逃げ遅れた。被害状況を確認しに来た役場職員を残して逃げることができなかったのだろうと推定される。
震災は生きのびた者の心にも深い傷を残す。ある記者は津波から逃げる際、老人とその孫の姿を目撃した。津波の写真を撮らなければと思った彼は、視線をカメラに移した。結局、老人たちを救助するタイミングを逸してしまった。記者はそれを悔やみ、自分を責め続けて慟哭する。
あの時に何が起きたのか、そして何が今も続いているのか、ぼくたちは考え続けなければならない。
※週刊朝日 2014年5月2日号