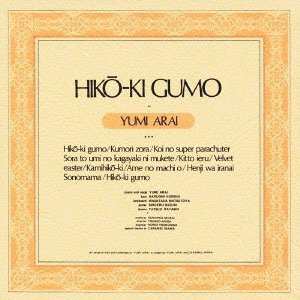

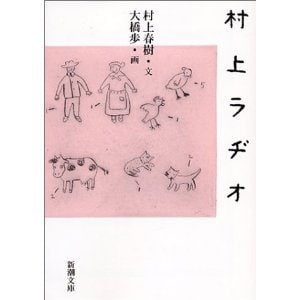
ノーベル賞の季節になると、毎年、世間を騒がしている方がいる。いや、騒いでいるのは、マスコミや世間のほうで、当のご本人が騒いでいるわけではない。もちろん、小説家村上春樹のことだ。
最近、村上春樹の著書を読んでいたら、こんな表現に出会った。
「ニール・ヤングの新譜CDを買ってきて、夕方包丁を片手に台所に立って、ごぼうとにんじんのきんぴらを作りながら一人で聴いていたら、あたりの空気がしみじみ化して、胸が熱くなってきた。ニール・ヤングって、きんぴらをつくりながら聴くとほんといいですね。」
この方は、初期のころから、食べ物のことをよく書く。そして、その文章を読むたびに、その書いているものが食べたくなってしまうのだ。
ついでだから、紹介すると、ロール・キャベツを作るときは「かつてプリンスと呼ばれたアーティスト」で、エリック・クラプトンはきのこうどんを作るのに向いているような気がする、と書いている。ちなみに、出典は『村上ラジオ』のなかの《きんぴらミュージック》。
思い出したが、村上春樹には、二度、お会いしたことがある。
一度目は、わたしが、大学を卒業して、最初の年、二十二歳のころだ。わたしは、地域情報紙の編集長だった。編集長といっても、周りの先輩たちに助けられながら、文章も写真撮影も一人でやっているような情報紙だった。
その中の企画で、近所のお店紹介のコーナーを作った。そして、そのシリーズの一軒として取材に行ったのが、村上春樹のお店『ピーター・キャット』だった。ファンの方はご存知だと思うが、村上さんは、作家になる前、ジャズ喫茶を経営していたのだ。だから、わたしは、作家になる前の村上さんに会ったことになる。
お店を紹介させてくださいというと、広告代はかからないのですね、と確認された。紹介させていただくだけなので、広告代はいりませんといった。それなら、ということで、小一時間は話したと思う。他のお店では、店長さんやスタッフの写真を載せていたのだが、村上さんのお店のときは、お店のキャラクターというか、お店のマッチにも使われていたイラストを使った。イラストは、英国の作家ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』のなかで挿絵として使われていたジョン・テニエルの「チェシャ猫」だ。たぶん、村上さんに写真はいやだと、断られたような記憶がある。エッセイの中で、自分の写真が嫌いだ、といっていたと記憶する。
お店の中には、猫の置物や小物がいっぱいあって、かつ、各テーブルには、木製の簡単なゲームやパズル、金属の知恵の輪などが置かれていた。そんなものが、お店の雰囲気を知的なものにしていた。
二度目に会ったのは、というより、このときは、見かけただけなのだが。
三鷹の日本茶専門の喫茶店だった。
当時は、日本茶専門の喫茶店というのが、まだ、珍しく、新鮮だった。
三鷹駅前の用水路わきに樹木に隠れるように建っていた小さな店だった。はす向かいに古本屋があって、わたしも、その古本屋で買った本をその喫茶店で読むことがあった。
一緒にいた友人が、
「おい、村上春樹だぜ」とわたしに教えてくれた。安西水丸さんの絵に、そっくりだな、と思った少し後に、どこかで会ったことがあるな、と感じたのだ。そう、以前、取材させていただいた、ジャズ喫茶の店主だった。
あれから数年がたち、村上さんは、群像の新人賞を取り、小説家村上春樹になっていた。
まだ、インターネットのなかった時代、彼の経営していたお店の名前は、なかなか確認できなかったが、場所などから、間違いないと思うようになった。もちろん、ネット社会になって、店の名も確認できるようになって、あのときの人が、村上春樹に間違いないことが確認できた。これも、不思議な思い出だ。ユーミンの《守ってあげたい》が、よく流れていた時代だった。
「松任谷由実コンサートツアー 2013-2014 POP CLASSICO」のスケジュールが発表になった。
ユーミンに関するわたしの思い出は、まだ、結婚する前の、荒井由実だったころからはじまる。
わたしが、ユーミンに出会ったのは、大学生のとき、小石川の図書館でだった。こちらは、本人ではなく、レコードだったけれど。
『ひこうき雲』と書かれたレコードの帯が、小石川図書館の視聴覚コーナーへ続く階段に貼られていた。貸し出しの新譜として紹介されていたのだ。
音楽雑誌によれば、そのアルバムは、はっぴえんどのメンバー、細野晴臣たちがバックで演奏していて、しかも、今までにない日本人離れした感性にあふれているという。
聴いてみたかったが、予約が詰まっていて、自分の番がくるまでには、ずいぶんたっていたように記憶する。今になって思えば、1~2ヶ月待たされたくらいだと思うのだが。
それまでのフォークとは、一線を画すような音だった。ギターのコードをかき鳴らしながら歌うフォークとは、まるで、異なる音楽だった。
すぐに、ニューミュージックという言葉が生まれた。
荒井由実は、ユーミンと呼ばれ、そして、アルバム数枚を残して、松任谷由実に変わってしまった。そこからの快進撃は、いまさら言わずとも、今の成人男女にはわかると思う。
ユーミンのすごさは、その曲作りのうまさはもちろん、その作詞のセンスだと思う。
作詞するために、OLたちにインタビューしたりするという話を聞いた事もあるが、その内容だけでなく、言葉の見つけ方、つなげ方にこれまでにない感性をみた。
ユーミンの歌は、松田聖子をはじめ、さまざまな歌手に歌われ、ヒットしている。ちなみに、松田聖子の作曲で出てくる呉田軽穂は、松任谷由実だ。ま、知らない方もいると思うので。なお、呉田軽穂は、作詞もする。
曲も作詞も素晴らしいユーミンだが、もうひとつ忘れてはならないのが、コンサートの企画。
大仕掛けなスペクタクル演出が楽しいのだ。わたしが、見たものでも、ステージ上にエレベーターをつけて、ステージの上から下へと、動き回っていたし、本物の象を連れてきたこともあった。あるときは、ステージにプールがあり、サーカスのメンバーと一緒だったり。ライヴというよりショーだった。それから、スキー場やサーフィンのメッカでコンサートをしたりもしていた。
昨年は、ユーミン、デビュー40周年ということで、プロコル・ハルムとのツアーも実施された。なぜプロコル・ハルムなのだろうと、少し、不思議だったのだが、今年、宮崎駿監督の『風たちぬ』の最後で、《ひこうき雲》が流れたとき、そのオルガンの音が、わたしの中で、プロコル・ハルムの《青い影》とリンクしたのだった。
今度のツアーは、どんな仕掛けがあるのか、楽しみだ。
追伸、うちの家人が、ユーミンの話が出るたびに、デビュー直後、渋谷のジャン・ジャンというライブ・ハウスで、ユーミンの弾き語りを見たと自慢する。少し、悔しい…[次回10/30(水)更新予定]
■公演情報は、こちら
https://yuming.co.jp/information/2013/09/02/2162/


































