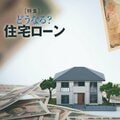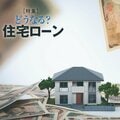昨今、前時代的な組織としてやり玉に挙がることが多いPTA。委員に任命されたりしたら、一大事だ。特に働く親にとっては死活問題。果たしてPTA委員になることにメリットはあるのか。
* * *
新年度、心機一転の子どもたちとは裏腹に、親たちには頭の痛い問題がある。PTAだ。
目的が明確でない活動、共働きやひとり親世帯が増えているのに、いまだ専業主婦を前提とした平日昼間の会合、会長以外で活動するのは母親ばかりという昔ながらの組織に、問題が山積していることは本誌でもたびたび報じてきた。
昨今、多くのメディアでこの問題が取り上げられることから、身構えている保護者も少なくないだろう。ただ、現実を知らずに、過剰に恐れられている面もある。
委員や役員なんかになったら大変だ、という文脈で語られることの多いPTAだが、新年度のクラス委員を決める小学校の保護者会で、低学年の教室をのぞいてみると驚くことがある。立候補する人が多いのだ。
多くの小学校のPTAには、「子どもが在籍する6年の間に必ず1度は委員をやること」という不文律がある。保護者の間では「早いうちにやったほうが得」とする説が定着しており、小学校1、2年生の頃はむしろ委員に手を挙げる人が続出するのだ。
都内小学校でPTA役員を務める女性も子どもが入学した3年前、ジャンケンで勝ち抜いて学年委員になったと話す。
「とにかく早めに済ませておくほうが負担にならないと、ほかのママから聞きました」
だが、低学年で委員をやると本当に得なのだろうか。筆者は数多くのPTA経験者を取材してきたが、ほとんど関係ないのでは、というのが実感だ。
そもそもなぜ低学年でやるほうがいいとされるかというと、一つは「高学年になると部長(委員長)にされやすい」と思われているためだ。だが、実際は学年に関係なく部長を選ぶことが多い。
埼玉県のPTAで広報部長を務める女性は、子どもが入学後すぐに委員を引き受けた。だが、広報委員を取りまとめる部長を決めるのはクジ引き。嫌な予感は当たり、1年生なのに部長に決まってしまった。最初は職員室の場所もわからず、先生の顔と名前も一致せず苦労したが、活動をしていくうちに慣れていったという。