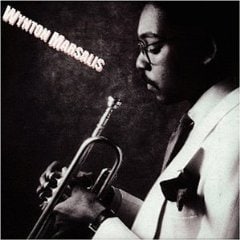
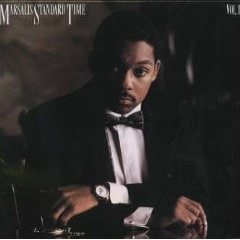
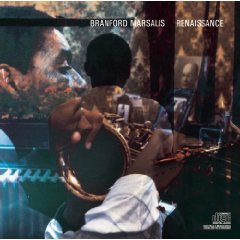
●マルサリス兄弟の衝撃
とにかく80年代前半はフュージョンの時代でした。といっても、誰もが右から左にフュージョンに興じていたというわけでもないのですが、あまりにもフュージョンという打ち上げ花火が派手だっただけに、アコースティック・ジャズを演奏している人たちは相対的に隅っこのほうに追いやられていたような気がします。
が、作用には反作用がつきものです。「アコースティック・ジャズって、なんてかっこいいんだ。俺も昔のジャズマンみたいにスーツを着て、4ビートをやるぞ」という連中が、80年代の中ごろから次々とジャズ・シーンに登場します。80年代初頭、颯爽とあらわれ、その先陣をきったのがウィントンとブランフォードのマルサリス兄弟です。
ふたりはニューオリンズ出身です。ニューヨークに進出後、まずウィントンがアート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズに加入しました。メッセンジャーズは当時、レコード会社との契約こそありましたが(今は大メジャーですが、当時は一介のマイナー・レーベルに過ぎなかったコンコード・レコードに)、“ああ、なつかしい。まだやってたのか”、“相変わらずかわりばえのしない音楽を…”的に捉えられていたところも、なきにしもあらずでした。しかしここに19歳のウィントンが参加し、バリバリにラッパを吹きまくったことでメッセンジャーズの株は急上昇。相変わらずのサウンドであるはずなのに、それがフュージョンに対する新鮮なカウンター・パンチにうつるという、世にも不思議なねじれ現象を引き起こしました。間もなくウィントンはブランフォードを呼び寄せ、マルサリス・ブラザーズは“ジャズ・メッセンジャーズに揃って参加した最初の兄弟”としても記憶されることになります。
●トム・ブラウン全盛期の終焉
82年に入ると、ウィントンは米コロンビア・レコードからファースト・アルバム『マルサリスの肖像』をリリースします。プロデュースはハービー・ハンコックです(演奏にも参加)。この時点で、最高の人気を博していたジャズ系若手トランペッターはトム・ブラウンでした。デイヴ・グルーシンのプロデュースで数々のフュージョン・アルバムを出していた彼は、まさに飛ぶ鳥を落とす勢い。ウィントンも当初、ポスト・トム・ブラウンのひとりとしてフュージョン風の作品でデビューする予定だったともききます。しかしウィントンはスーツを着て4ビートのアコースティック・ジャズを演奏する道を選びました。
ネクタイを締めてスーツでジャズ…今でこそ時代が一回りしてしまいましたけれど、当時は明らかに「アナクロ」でした。「大昔のジャズ・スタイル」と同義語でした。いまさらモダン・ジャズ・カルテットやオスカー・ピーターソンじゃあるまいし、というわけです。今や絶対にスーツでしかステージに立たないロン・カーターですら、当時は毛糸の帽子をかぶり革ジャンをはおって演奏していました。スーツを着ないことがヒップだったのです。だけどウィントンはスーツ、ネクタイを堂々と身につけて、超絶技巧をフルに駆使したアコースティック・ジャズを居丈高なまでにプレイしました。その音楽は、よくいえば非常に高度、だけど私にとっては、いささか肩の凝るものでした。
しばらくブランフォードを加えたバンドで活動していたウィントンですが、85年の半ばからワン・ホーン・カルテット編成に切り替えます。ブランフォードが、スティングからのオファーを受けたことが原因で、兄弟が仲たがいしたとの説も流れました。「兄貴はロックに魂を売ったんだ。そんなヤツとは共演するもんか」とウィントンが言ったとか言わないとか。
●ウィントンvsブランフォード
87年、ウィントン・カルテットは『スタンダード・タイムvol.1』というアルバムを発表します。超絶技巧で知られたウィントンが、テクニックの限りを尽くしてスタンダード・ナンバーをこなごなにする、というものです。1小節ごとにテンポが倍になる《枯葉》や、テーマ・メロディを激しく分断する《ザ・ソング・イズ・ユー》を聴いて、私はあまりのテクニックに圧倒されました。が、ここまでトリッキーにする必要はどこにあるのだろう、ウィントンたちは技術をもてあましているのではないか、と感じたのが正直なところです。
しかし、ほぼ時を同じくして発表されたブランフォードの『ルネッサンス』、および89年の『トリオ・ジーピー』には、素直に入ってゆくことができました。とにかくサックスを吹く、それ以外は考えていない。当時のブランフォードには、そんな潔さがありました。とくに『トリオ・ジーピー』は、当時すでに80歳になろうとしてい巨星ミルト・ヒントンが特別参加し、猛烈に力強いプレイで、祖父と孫ほど歳の離れた主人公のサックスを煽りに煽るのです。当時のジャズ・ベース界は、形こそウッド・ベースであっても、実際の音はアンプまみれ、というケースがあまりにも多すぎました。が、ヒントンはアンプのプラグを抜いて、張りのある力強い音色で、若手ブランフォードにカツを入れます。これほど燃え上がった(といっても、スマートさは失われていませんが)ブランフォードは他のアルバムでは聴けないはずです。
このあたりのアルバムが、50年代や60年代のジャズ名盤と同じように未来永劫語られていくとは思えませんし、私も別に無理に聴けとはいいません。だけどマルサリス兄弟の奮闘がなければ、ひょっとしたらアコースティック・モダン・ジャズは消滅していたかもしれない。洒落にならない状況に追いこまれていたかもしれない。と考えると、彼らの旧作に耳を傾けながら、80年代のひとこまに思いを馳せるのも、決して無駄なことではない。そう言うことはできます。


































