読者アンケートで多かったのは「つまずきの克服法を知りたい!」という声。算数指導が人気の辻義夫先生に、つまずきの原因と家庭でできる対処術を教えてもらいました。子育て情報誌「AERA with Kids2025年夏号」(朝日新聞出版)からお届けします。
【図】算数のつまずきやすい単元3つはこちらつまずき対策の近道は 数量感覚をつけること
子どもの算数のつまずきについて、親は「つまずいた単元の学習内容の理解不足」と思いがちです。しかし、辻義夫先生は、「それもありますが、実際は、それまでに“数字の感覚”と“量や長さの感覚”がしっかり身についていなかった可能性があります」 と指摘します。
そのことが5年生になって、「割合」や「速さ」といった抽象概念の多い学習に入ったとたん、「お手上げ!」になってしまうのです。
ここで脱落してしまうと、それ以降は算数も数学もきらいになるケースが多いとか。
「算数は積み上げの科目。学年にこだわらず、理解できていないところまでさかのぼって、数字の感覚や量・長さの感覚を身につけることが大事です」(辻先生)
子どもは、習ったことと新しく出てきた概念を結びつけるところでつまずきがち。だから手っ取り早く公式を覚えて、数字を当てはめれば答えが出るような作業を好みます。速く解くことよりも、じっくり考えて理解する習慣をつくっていくほうが、結局はつまずき対策の近道になるのです。
つまずきやすい3つの単元

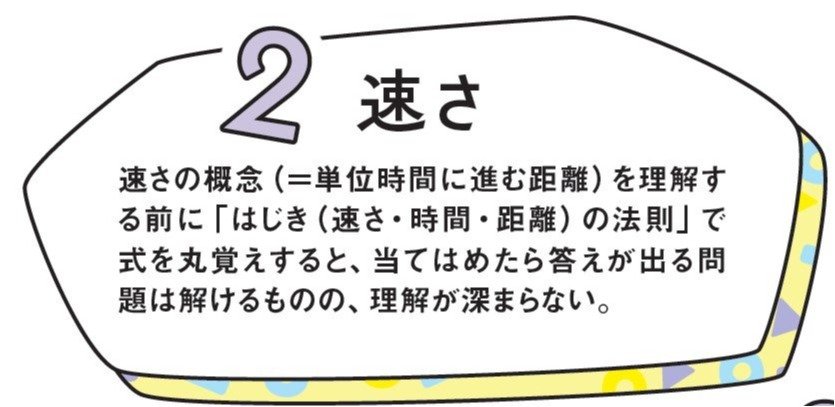
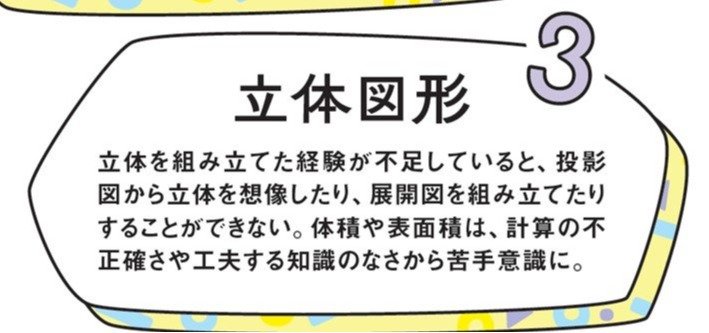
つまずき別アドバイス〈理解不足〉
読者のみなさんから届いた「つまずきポイント」をまとめたところ、〈理解不足〉〈うっかりミス〉〈文章題〉の三つのキーワードが! お悩みを相談しました。
○かけ算・わり算・分数の概念すらわかっていない気がします。どう教えたら?
かけ算は「小さいものを集めて全部でいくつになるかを計算する手段」、わり算は「大きなものを細かく分けて、一つのかたまりがいくつになるかを計算する手段」という、そもそもの意味をていねいに伝えてみてください。「お菓子が〇個入った袋」のような例をあげ、絵や図にすると理解しやすくなります。
分数は「何個に分けた何個分」から始めます。高学年なら「もとの大きさが違えば、同じ3分の1でも大きさが違うこと」に気づくことが大切です。
次のページへうっかりミスのつまずき









































