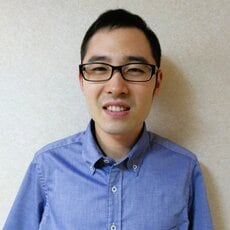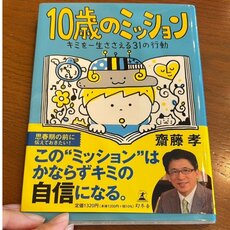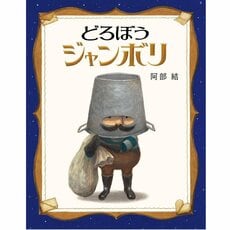「お願いだから学校だけは連れていって」と母は泣きながら私に訴えた。
「小沼さんは優しすぎる。もっと厳しくすれば学校行くよ」と言う友達もいた。
「学校に行かせるのはやっぱり親としての責任だよね」と言われたこともあった。
日中、子どもだけで家で過ごしていたので、児童相談所の方も2回ほど訪ねてきた。私が虐待していると疑われ、近所の誰かが通報したと思うと、外へ出るのが怖くてたまらなかった。
両親も、夫も、先生も、友達も、近所の人も、誰にも理解してもらえない。本当につらい孤独な日々だった。
私だって自分の考えが正しいかどうかなんてわからない。「学校に行かなくて絶対に大丈夫なのか?」とみんなに責められても、私だって本当はわからない。でも、子どもを苦しめることが良い未来につながるとはどうしても思えなかった。
子どもを傷つけるような人は子どもに近づけたくない、たとえ夫や両親であろうと。子どもが元気で過ごせるような環境を作るために、私が子どもを守る。そんな必死の思いだった。
きっと周囲から見た私は、鬼のように怖かったのかもしれない。
私にとって息子の不登校は、息子が学校へ行く行かないの問題ではなく、子どもの命を守らなくてはならないという問題だった。子どもが元気でいられる方法を誰か一緒に考えてほしかったのだが、それを理解してくれる人はいなかった。
周囲がなんと言おうと、私が「してほしい」と求めたサポートだけをしてくれる人がいたらなんてありがたかったか。良かれと思っての余計なアドバイスはいらないのだ。当時、私が感じたその思いは、今、私が子どもたちにしてあげたいことである。
※第1回<「嫌がる息子を小学校へ連れていくことしか頭になかった」 不登校の息子と向き合った母が考えを変えたきっかけとは【体験記】>から続く