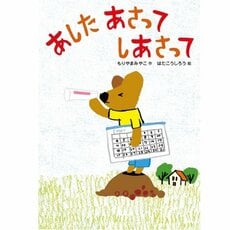――いわゆる「男性の産後うつ」に関しては、SNS上で批判もありました。
「男性の産後うつ」が批判される背景には「男性は産みもしないのになんで産後うつやねん」という考えが根底にあるのだと思います。
確かに女性の産後うつは妊娠出産に伴うホルモンバランスの崩れが主な原因です。ただ、ビッグデータから見ると、うつ傾向にある男性は女性と同じくらい産後うつになるリスクがある、ということが分かってきました。主な原因は環境の変化です。子どもが生まれるプレッシャーや会社・夫婦間の関係性の変化が引き金となる。中には父母共に産後うつ傾向になるカップルもいます。でも今までは見落とされていました。産後うつは女性特有のものであり、男性は関係ないと捉えられていたからです。父親もちゃんと支援の対象にする必要があります。
「男性の産後うつ」という言葉はちょっと炎上していましたが、このマニュアルが社会的な注目を浴びるきっかけにもなりました。父親支援という考え方が世の中には必要なんだ、というプラットホームを社会に作った。それが『父親支援マニュアル』の一番大きな特徴であり役割かなと思います。
妊娠・出産・子育ての支援対象を男性にも広げる
――このマニュアルには父親支援の必要性や方法の解説が書かれていますが、自治体向けに作成した理由を教えてください。
そもそも僕がこの研究を始めた20年前は、「父親支援って何ですか」「なんで父親が育児しなきゃいけないんですか」という感覚が当たり前でした。そのあとに父親の育児を支援するNPO法人「ファザーリング・ジャパン」ができたり、イクメンという言葉ができたりして、やっと男性の育児が社会の中で認識されるようになりました。今は育休制度の拡充などにより、男性が育児する土壌は整ってきています。ただ、実際にできているかというとそうでもない。さまざまな要因がありますが、僕たちが着目したのは、支援していく社会の文化やシステムがないという点です。
次のページへ江戸時代の子育ての中心は男性⁉