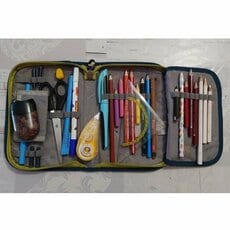「親が動けば動くほど、子どもは動かなくなります。親は、肩の力を抜いていいんです」と教育評論家の石田勝紀さん。「イライラしないで楽しく過ごしたいと思っているのは親も子も同じ。親の遊び心が子どものやる気を引き出すことを忘れないで」と続けます。
新渡戸文化アフタースクールの織畑研さんは「○○しなさいというような圧迫的なコミュニケーションを減らし、親子関係を穏やかにするためにも、子ども自身が時間管理をできるようにしたいですね」と話します。
アンケートには「学習中、きょうだいが騒がしい」「自室があるのに行かない」という声も。「でも雑音の中で集中できることは強みになります」と織畑さん。
「社会に出たら、雑音や中断がある中で仕事をしないといけませんから。ゴチャゴチャの中でも大丈夫。対応力がついていきます」
早いうちからの伴走で習慣化に
アンケートの「わが子は学習習慣がついていると思うか」という質問に「ついている/大体ついている」と答えた人は、「低学年(または就学前)から机に向かう習慣をつけることを意識した」「スケジュール表をつくっている」といった回答が多く見られました。早いうちから親が伴走したことで習慣化につながっているケースが多いようです。
とはいえ、興味を示すことも、成長のスピードも子ども一人ひとり違って当たり前。大人の都合で考えすぎず、成長は一足飛びにはいかないことも心に留めておきたいものです。
鎌倉小学校教諭の根本哲弥さんは、「啐啄同時(そつたくどうじ)」という言葉を教えてくれました。
「卵から雛(ひな)がかえろうと殻の中で音をたてた時、親鳥がすかさず殻を外からついばんでやり、雛が殻を破るのを助けることを言います。キラキラにあふれた低学年の子どもたちは大好きな親に褒められたいと思っています。子どもが殻を破ろうとする姿を見逃さず、寄り添う言葉をかけていきたいですね」
(取材・文/岩崎美帆)
朝日新聞出版
![AERA with Kids (アエラ ウィズ キッズ) 2025年 春号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZlxSacAZL._SL500_.jpg)