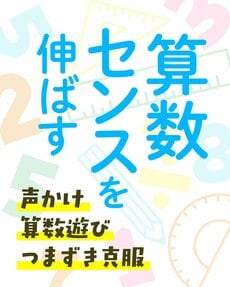長男は小さいときから漢字が気になる子で、道端で気になった漢字をメモしてくるような子でした。たとえば公園で「ボール遊び禁止」という看板を見ると、「禁」の字を「ききにしょう」って分解するんです。上には「木」が2つ、その下に「二」、その下に「小」で「禁」だから「ききにしょう」。
――着眼点がおもしろいですね。
そうなんです。息子たちは小5と小3になりましたが、「普通」の部分が増えてきちゃいました。「あのころのおもしろい言葉を、もっとメモしておけばよかった」と後悔しています。
もっともっとおかしな言葉があったはずなのに、思い出せない。もったいないことをしたな、と。
息子に「クソつまんねえ」と言われたら
――お子さんたちは言葉への感受性が高いような気がしますが、やはり作詞家であるいしわたりさんの影響があるのでしょうか。
あると思います。ぼくは家で仕事をしているので、子どもたちとすごくよく話すんです。普段から親子でもよく話すし、子どもそれぞれと2人だけで旅に出たりもします。
――どんな会話を心がけているのですか?
子どもを子ども扱いせずに、対等に話すようにしていますね。難しい言葉も遠慮せず使います。わからなければ質問すればいいし、なんとなくわかって聞いているならそれでもいい。言葉ってそうやって覚えるものなので、手加減せずに話しています。
「こんな言葉を使ってみたい」とか「かっこいい」と思ってもらいたいし、子どもは背伸びをするから成長すると思うんです。
――でも、小5といえばプレ思春期です。「言葉が悪くなって困る」と嘆く親御さんも多い時期ですが……。
長男はまさしくそんな感じです。ちょっと前までかわいい言葉を使っていたのになぁ(笑)。
悪い言葉も成長の一環だと思うんですが、あまりにひどい場合には「その表現はよくないよ。もっといい言い方がある」と伝えます。
――たとえばどんな言葉ですか?
息子は最近よく「クソつまんねえ」って言うんです。だから「つまんない」はいいけど「クソつまんねえ」はダメ、「クソ」はよくない、と言います。
次のページへ話し言葉を学ぶのが家庭