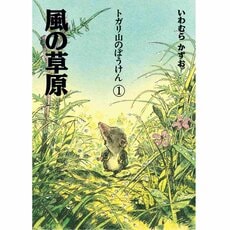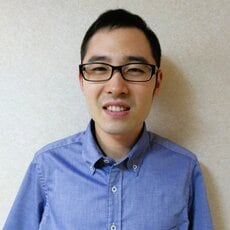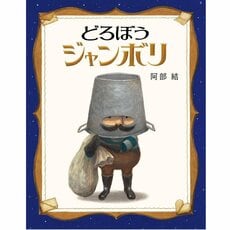でも、しばらくしてその先生に「早く靴代払って」と言われて……。先生が気にしていたのは、私の靴が盗まれたことではなく、自分が渡した靴のお金だったんです。「いじめを見て見ぬふりした大人」に絶望しました。その後、一切学校に行かなくなり、卒業式にも出ませんでした。

――ご家族の反応はどうでしたか?
中川 幼いときに父を亡くしているので、母が女手ひとつで私を育ててくれていました。最初は、「どうしたの? 何があったの?」と優しく接してくれていましたが、恥ずかしくて、いじめられていることをどうしても話せなくて。部屋に鍵をかけて閉じこもる私に母もだんだんいらだち、「義務教育なんだから行きなさい! ダメ人間になるぞ!」と怒鳴り、ドアをこじ開けて入ってきましたが、私は「行かない!」の一点張りでした。私が怠けているようにしか見えなかったんでしょうね。でもそんな母も、私が毎日塞ぎ込む様子を見て、最終的には学校に行かない選択を受け入れてくれました。
――これまで数多くの不登校の人たちの話を聞いてきましたが、つらいのに学校に行っているときが一番苦しかったと言います。中川さんは学校を休み、どのように毎日を過ごしていましたか?
中川 ひたすらネットやゲームをして、ダラダラしていました。当時はインターネットが世に広まりはじめて間もないころで、23時から「テレホーダイ」というネット使い放題の時間があったんです。夜な夜なブルース・リーのマニアの人たちとチャットをしたり、好きな戦隊モノやフィギュアについて調べたり、同じ趣味の人と外の世界でつながることは、ギリギリの精神状態だった私の唯一の救いでした。夜遅く、母が仕事から戻るのを寝ずに待っていて、お風呂場までついていき、その日ネットで得た情報をひたすらしゃべっていましたね。疲れていただろうに、黙って聞いてくれて、たまに笑ってくれて。その時間が心の支えになっていました。
16歳の誕生日から始まった、私の“上書きチャレンジ”
――その後、お母さまが探してくれた通信制の高校に進学されましたが、そこでの生活はどうでしたか?
中川 同じように不登校を経験した子のほか、ヤンキーやギャル、芸能人までさまざまな人がいましたが、中学のクラスのような排他的な雰囲気はなく、クラスメート同士が互いの個性を認め合う風通しの良いところでした。それでもいじめられた記憶は消えず、「どうせ嫌われる」「もうイヤだ」「消えたい」というネガティブなことばかり考えてしまい、衝動的に死のうとしてしまったことも……。決して私の前では弱さを見せることのなかった母が、その日は「バカ!」と涙を流したのを覚えています。
次のページへ偶然ジャッキー・チェンに会えた