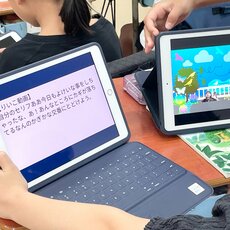◎ゲーム2 産地収集マッピング(社会・地理)
「食材の産地をチェックして、白地図にシールを貼ろう!」
ふだん、家で食べる食材や加工品が「どこで作られているのか」を知ることは、自分の住む地域だけでなく都道府県への興味関心につながります。買い物から帰ってきたら産地をチェックして、白地図にシールを貼ると盛り上がるはず。埋まらない地域が出てくると、探したくなります。
【学びPOINT】
野菜は赤、魚は青、果物は黄色など食材ごとに色の違うシールを貼ると、気候や風土による特産品の違いにも気づきます。
学び×ゲームのアイデア シーンB.キッチン
◎ゲーム3 浮くor浮かない?野菜クイズ(浮力・密度)
「大人でも意外と難しい野菜の密度を体感せよ!」
野菜が水に浮くか沈むかは、「重さ」ではなく「密度」が関係しています。野菜を洗うとき、「どっちだと思う?」と予想をたててみて。一般的に「土の上にできる野菜は浮きやすく、土の下にできる野菜は沈みやすい」そう。タマネギが浮く理由は、タマネギ畑を見るとわかるかも?
【学びPOINT】
例外の一つは、トマト。糖度が高いと密度も高くなって沈むそう。実際に食べ比べて、甘さの違いを確認してみて!
◎ゲーム4 野菜の切り口予想クイズ(空間図形・植物)
「どんな形? どんな色? 野菜を切る前に当てよう」
野菜の中身を予想して切るだけでも、子どもにとってはゲーム。切る位置や角度で断面が変わるので、空間図形の特徴を認識する力がつきます。切り口を撮影して図鑑を作ったり、色を塗ってスタンプにしたりするのもオススメ。
【学びPOINT】
「種はある?」「どこから水を吸い上げるのかな」と野菜の特徴にも注目すると、植物への興味につながります。
◎ゲーム5 最高の目玉焼き実験(比較実験)
「自分にとって最高のおいしい目玉焼きとは?」
予想をたて、実験して観察する、まさに理科体験をできるのが「料理」。特に目玉焼きは、時間や火力、水やふたの使用など条件で出来上がりが変わるので、比較実験におすすめです。有名シェフの目玉焼きレシピを比べても楽しそう。
【学びPOINT】
時間や火力など条件と結果を記録すると、理解が深まります。手順を教えるだけでなく、子ども自身が考える時間が重要!
(取材・文/AERA with Kids編集部)
朝日新聞出版
![AERA with Kids (アエラ ウィズ キッズ) 2024年 冬号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51gSqY6VxmL._SL500_.jpg)