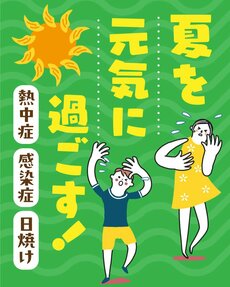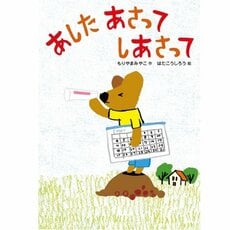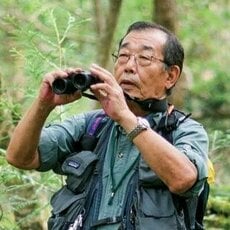安浪:そうです。まずは親自身が、子どもがやっていることの全貌を把握することですね。いろいろなご家庭に入って指導していますが、「今週塾で何やりました?」と聞いたときに、親御さんから「今回は図形でした」とか、「場合の数でした」とか、「今週の社会は江戸時代でした」とかすぐ出てくるおうちは、親御さんがお子さんの勉強内容をきちんと把握できているんだなと思います。カリキュラムがあるわけですから、それに目を通したり、子どもから聞いたりすればわかるはずです。逆に全然わからないです、とか本人に任せています、というご家庭は管理云々以前の問題かな、と。でも、実際はこのようなおうちが半分以上かもしれません。
■「やったの?」では解決にならない
矢萩:保護者が問題を解けるようになる必要はありませんが、子どもが今何を勉強しているのかを把握しておくことは大事です。それがわかっていれば、「頑張ってるね」という言葉も自然に出てきますし、何より説得力があります。ちゃんと見守っていてくれる親のそういう言葉から、子どものやる気って出てくるのかな、と思います。
安浪:あとはとにかくやることを大きいものから細かいものに分け、それぞれを細分化することですね。漠然と「やったの?」では解決にならない。例えば、「どうサポートしていいかわかりません」という相談を受けた時、まず「教材の整理は家庭内でどうなっていますか?」から聞きます。子どもに丸投げと答える方に「まず教材の整理をしてください」とお願いすると、「どう整理をしていいかわかりません」と……それじゃあ、子どもだって整理できないですよね。その場合は、「大きい箱を科目分、まず4個用意してください」とお願いします。子どもには「君はリュックから中身を全部出してね」と言い、「お母さんはそれを、国、算、理、社と教科ごとに箱に入れてください」と。それぐらいやることと分担を細かく分けていく。
矢萩:そもそも小学生くらいの年齢だと、先のことを考えて逆算的にスケジュールを立てることは苦手なんです。大きな目標と、来週までにやることを決めるくらいで精一杯です。なので、それをやる理由をちゃんと合意形成して、今日やることをすぐ分かるようにすることがスケジュール管理サポートの要です。
次のページへ親としてはめんどくさい