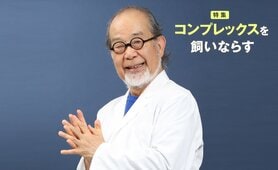気がかりなのは、嘉人君が最近、「どうせ僕はこの見た目だから」と、外見をうまくいかない理由にすることだ。これから他者からの評価が特に気になる思春期にも入っていく。博美さんは「きっと悩むと思うんです。それを、どう消化するのか。親としてできる限りサポートはしていきたいですが、最後は本人次第です」と話す。
天野夫妻はこう口をそろえる。
「嘉人はたくさんの喜びや経験を与えてくれました。外見なんかよりも内面の格好よさが大切だって、教えてもらった。トリーチャーコリンズ症候群であることも含めて嘉人が大好きです」
子どもを育てるなかで親も成長し、考え方をアップデートしていく。それは私も同じだ。長男を通し、私の中の偏見に気づかされることがたくさんあった。うまく笑顔の表情をつくれない長男の疾患を知ったとき、「まだ男の子でよかった」と思った。「女性のほうが、外見が重視される」という考えが私にあったのだろう。
そもそもどうして、私は長男の将来を不安に感じるのか。「笑顔は大事」。そんな誰もが疑わない社会通念がある中で、「左右対称の普通の笑顔でなければならない。ゆがんだ形の笑顔では受け入れてもらえない」と私が思い込み、長男の将来を悲観していたからだ。
そんな偏見を解きほぐしてくれたのは、長男だった。彼が屈託なく楽しそうに笑う姿を見ていると、少々ゆがんだ表情であっても、つくり笑いなんかよりよほど魅力的だと教えてもらった。
数々の当事者に取材してきて、私が感じているのは「顔には慣れる」ということだ。拙著『この顔と生きるということ』でも触れたとおりだ。確かに初対面では驚くかもしれない。でも、コミュニケーションを取るうち違和感は薄まり、普通とはちょっと違うかもしれない外見も特徴の一つに過ぎなくなる。そうなれば、性格や表情、しぐさ、声色、服装、トータルな人間性を見ることができる。
当事者は社会に適応するため、そして幸せになるために努力をしている。でも、本当はそんな努力はしなくても、生きづらさを感じないことが理想だ。そのためには、社会が「見る目」を変える必要がある。外見の多様性を認め、タブー視しない。私の長男について言えば、「うまく笑えなくたっていいじゃないか」と、多くの人が受け止める社会になってくれたらと願っている。(朝日新聞記者・岩井建樹)
※AERA 2019年10月21日号より抜粋