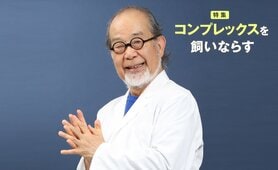1月下旬から続く世界同時株安が、安倍政権に揺さぶりをかけている。アベノミクスで景気回復への期待は膨らんできたが、賃上げ前に息切れしそうだ。
株価の変調を招いた原因のひとつは、米連邦準備制度理事会(FRB)が今年初めから、量的緩和の縮小に乗り出したことだ。市場にお金を流すペースを緩め、投資家が株式や新興国の通貨を買ってきたお金を引き揚げ始めた。最初に影響を受けたのが、アルゼンチンの通貨「ペソ」。対ドルで昨年12月から3割も価値を下げた。
「投資家のマネー引き揚げの矛先が、経済が脆弱なアルゼンチンの通貨に向かった格好です」(第一生命経済研究所の西濱徹さん)
その後、トルコの「リラ」、南アフリカの「ランド」、ブラジルの「レアル」などに飛び火。トルコや南アフリカは通貨安を食い止めるため、金利を引き上げて投資家の引き留めを図ったが、効果は乏しいようだ。
景気回復がいわれ、日本車などの好調な販売を支えてきた米国経済にも、不穏な気配が漂い始めている。雇用や製造などの経済指標が芳しくない。みずほ証券チーフマーケットエコノミストの上野泰也氏は解説する。
「量的緩和の縮小・停止は必要なプロセスです。たとえて言えば、子どもの予防注射のようなイベントであり、一時的に泣き叫ぶなど騒ぎは起きるものの、時間がたてば、状況は次第に沈静化するでしょう」
こういった事情から投資家は今、リスクが比較的小さい先進国の債券にお金を移しているという。ただ、日本国債を買うには、まず円を買わないといけない。これが円高を招くことになり、年初には1ドル=104円台だった為替相場が一時、100円台に急騰した。円高になれば、自動車や電機製品の輸出にはマイナスだ。
※AERA 2014年2月17日号より抜粋