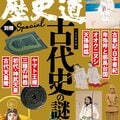食後に酒を呑む場合、政宗はうがいをしてから呑んでいる。食事に親類の者が一人でも同席していれば、うがいはしなかったが、普段は酒を呑むことはなかった。食事中は、政宗を楽しませるため家臣たちがおのおの芸を見せたが、それが終わると湯を所望した。つまり、食事は終わりということで膳を下げさせ、茶菓子の用意をさせたのである。お茶の用意をさせている間に厠へ向かったが、相伴衆も同じだった。
一同が厠から戻ると、茶を飲み菓子を食べた。お茶の時間が終わると相伴衆は席を立ち、朝食は終了となる。なお、相伴衆との朝食の慣習は珍しいかもしれない。
その後、家臣たちが入れ替わり政宗の前に現れ、政務の時間となる。これが午後2時まで続き、政務は終了となる。政宗の時代はまだ1日2食の時で、昼食は取らなかったことが確認できる。 政務が終了すると、城の奥に引き込み、再び「閑所」に入った。朝と同じく、側近からの報告を受け、指示を与えた。この間はプライベートで余暇を楽しむ時間でもあった。

夕食の時が近づくと、再び風呂場に入って行水となるが、その前に夕食の献立について、朝食の時と同じく食べたくないものがあれば指示を与えて修正させた。行水、夕食の後は就寝となる。
政宗に限らず、大名には守るべき一日の予定がこのようにあらかじめ課せられていた。もちろん大名によって内容に差異はあったが、それに従って行動するよう求められたことは共通している。
そうした事情は江戸屋敷で暮らす場合も同じだが、江戸在府中は月に3回ほど、江戸城に登城して将軍に拝謁することが幕府から義務付けられていた。登城日以外のスケジュールは国元にいる時と同じだが、国元と比べると江戸での生活は堅苦しいものだった。幕府の監視下にあったため、登城日以外は屋敷外に出ることを自粛せざるを得なかったからである。
こちらの記事もおすすめ 【イラスト解説】伊達政宗の1日スケジュール! 起床から就寝までどんな過ごし方をしたのか?