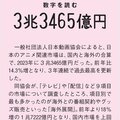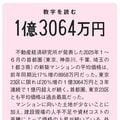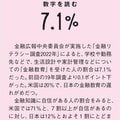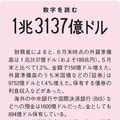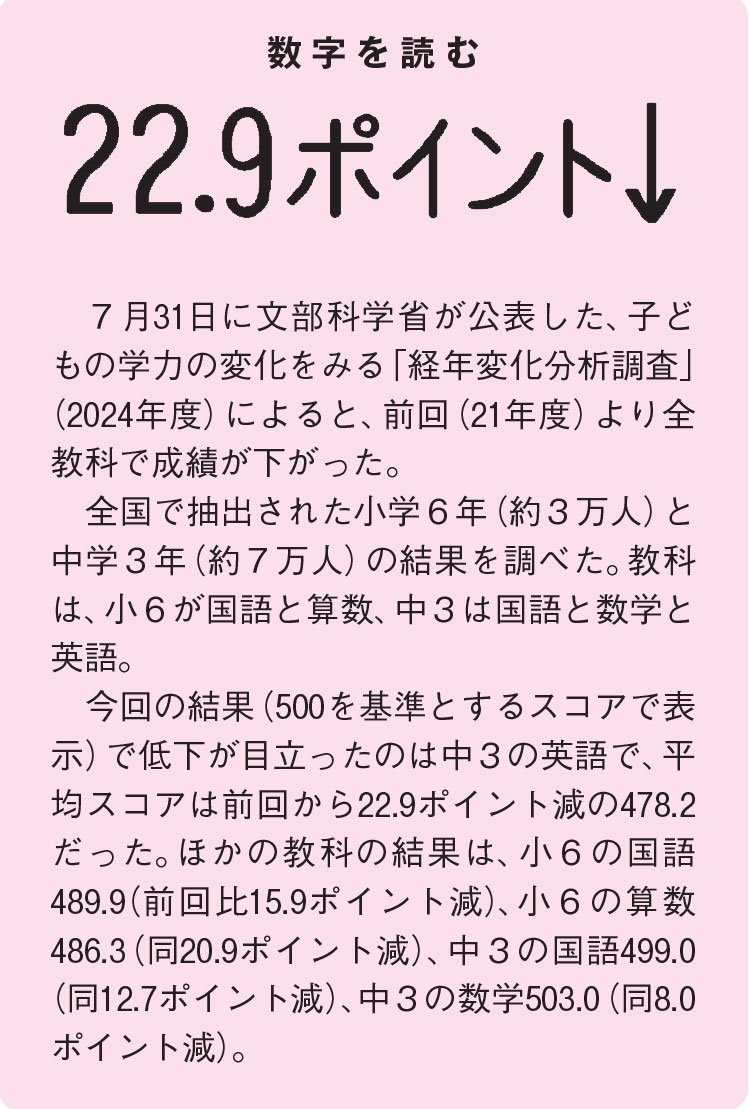
物価高や円安、金利など、刻々と変わる私たちの経済環境。この連載では、お金に縛られすぎず、日々の暮らしの“味方”になれるような、経済の新たな“見方”を示します。 AERA 2025年8月25日号より。
* * *
清々しい「こんにちは」の声。
講演で訪れた札幌の高校のグラウンド横を歩いていると、ユニフォーム姿の野球部員たちが次々と元気よく挨拶してくれた。広々としたグラウンドで、大きな声を張り上げ、みんなのびのびと体を動かしている。夏の東京の炎天下ではなかなか見ることができない、爽やかで心地よい光景だ。
「こんな環境で子どもを育てたいですね」と隣を歩いていた先生に声をかけると、「北海道は教育格差が深刻なんです」と意外な言葉が返ってきた。
北海道では地方の過疎化が進み、1学年が1クラスだけという高校が珍しくないそうだ。十分な教員の配置も困難なため、2021年度からは「T−base(北海道高等学校遠隔授業配信センター)」が設置され、道内の32校に授業をオンライン配信しているという。少子化が進めば、全国各地で同じような問題に直面する学校は増えていくだろう。
7月31日、子どもの学力の推移を追跡する「経年変化分析調査」(24年度)の結果が公表された。調査対象は小学6年生と中学3年生で、小6は国語と算数、中3は国語・数学・英語が対象となっている。驚くべきことに、全ての教科で前回調査よりスコアが大幅に下がっていた。
文部科学省は「継続的な分析が必要」と慎重な姿勢を崩していないが、有識者からは「深刻な事態」と危機感が示されている。
スコアが下がった理由の一つは、スマホやゲームに費やす時間が増え、学校外での勉強時間が減っていることのようだ。さらに注目すべきは、学力の平均スコアが下がっただけでなく、経済的な背景や文化的な背景による格差が明確に広がっていることだ。
文科省の分析によれば、家庭にある本の冊数が25冊以下の家庭の子どもたちは特にスコアが大きく低下していた。その下げ幅は、本が多い家庭に比べて最大4.5倍にも達するという。