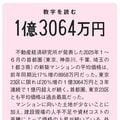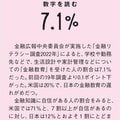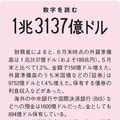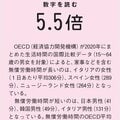競争原理がもたらす結果としての格差はある程度は許容する必要があるが、生まれた環境や家庭状況による教育格差は望ましくない。子どもの頃の教育格差は、大人になってからの経済格差につながり、さらに次世代の教育格差へとつながる。
格差が固定化されると、努力をしても報われないという閉塞感が社会に漂うようになる。それが現代日本に感じる息苦しさの一因ではないだろうか。
札幌での講演は全国の高校の社会科の先生に向けた金融教育がテーマだったが、最近は金融機関が投資を勧めるための「金融商品教育」が幅を利かせている。「投資」と聞けば、すぐに金融商品を購入することが連想されるが、本来、生徒たちは投資される側の立場のはずだ。
長期的に最も高いリターンをもたらす投資は教育であると言われている。これから少子化が進むことを考えると、貴重な人材を育成することはすべての国民にとっての利益につながるのは明らかだ。政府は目先の経済成長の数字にとらわれず、教育格差の縮小のために、公教育にこそ積極的な投資を進めてほしいと強く願う。
※AERA 2025年8月25日号
こちらの記事もおすすめ 「鬼滅の刃」から学ぶ“分断のない社会” アニメから“日本のファン”増やし繋がる世界の輪 田内学